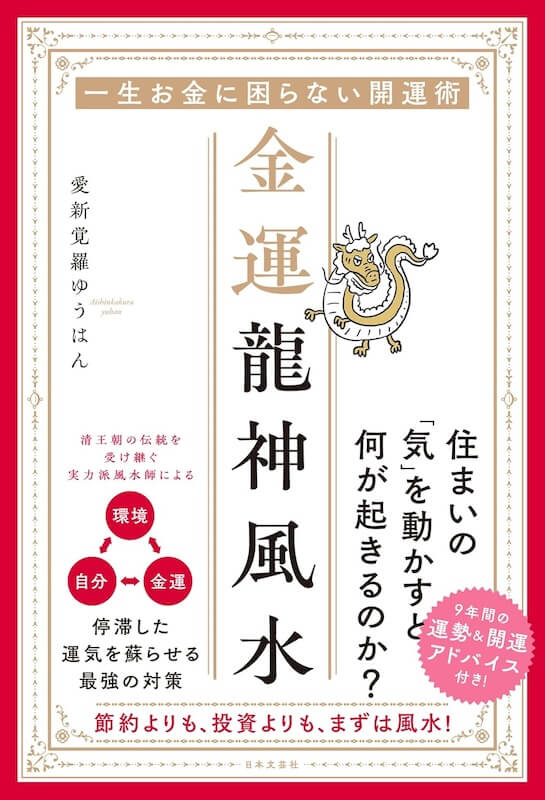お金が“流れる”人には3つの力がある?【金運龍神風水】
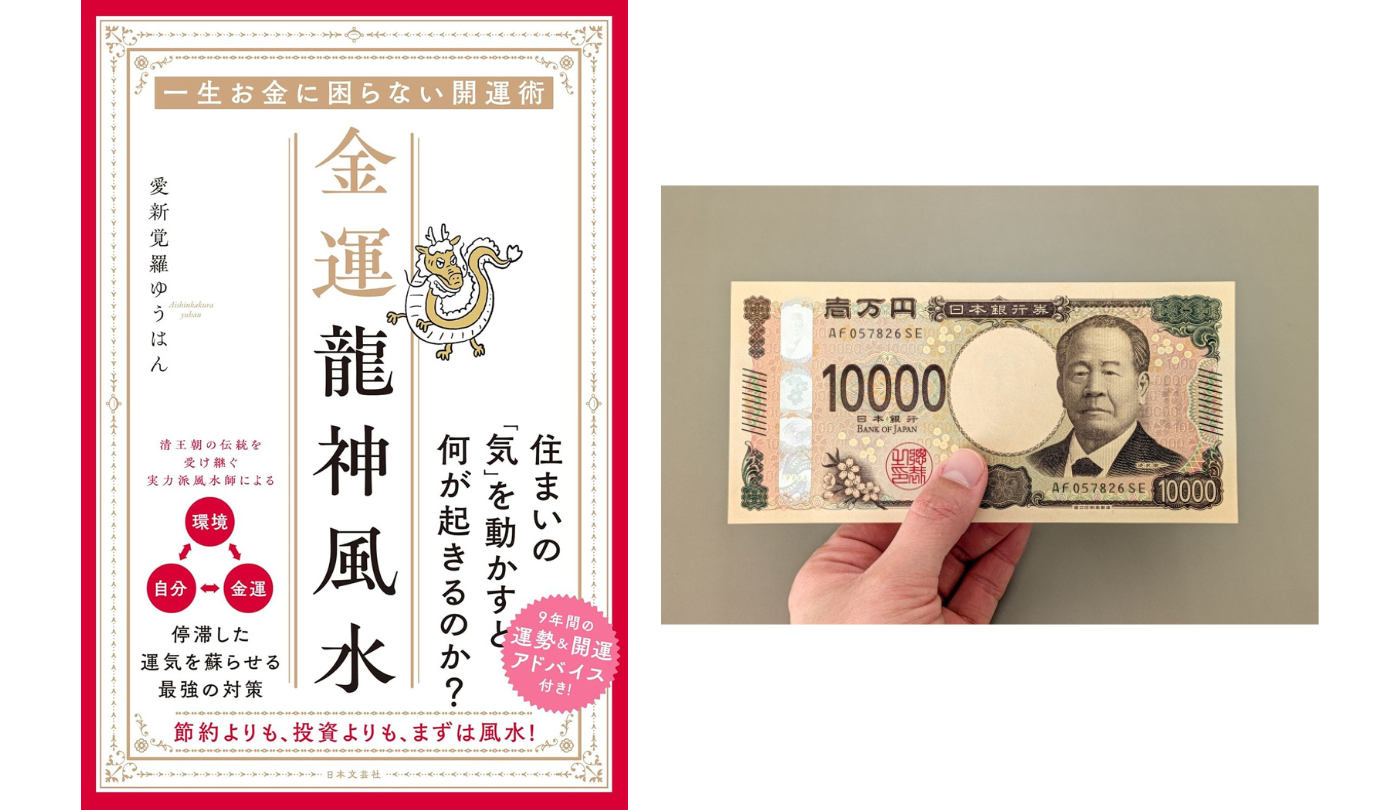
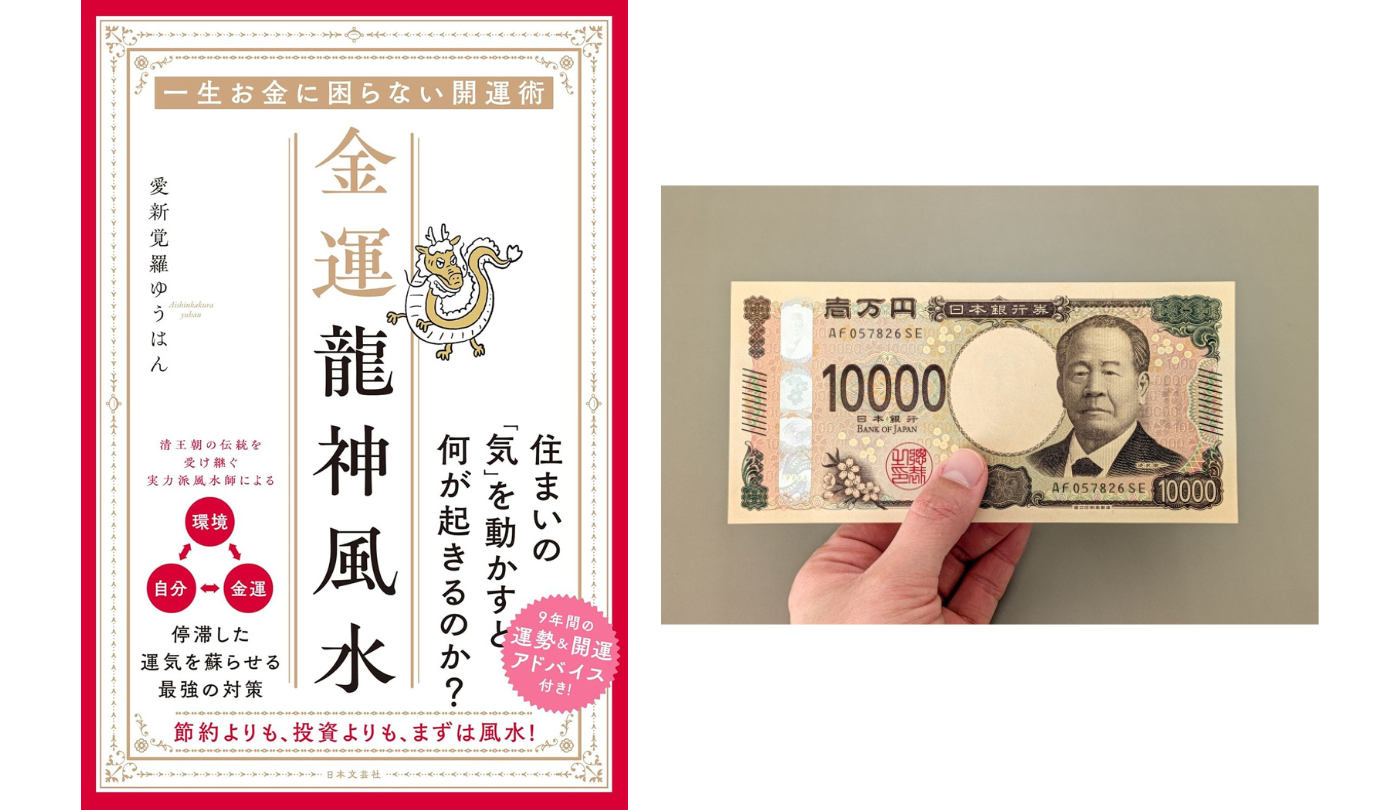
金運をめぐらせる3つの力を知る
これまで中国のお金持ちが学んでいることや部屋の特徴、メンタル、龍神パワーなどについてお伝えしてきましたが、ここでは彼らが金運を動かすためにもっとも重視している、3つの力についてお話ししていきます。
お金は「天下のまわりもの」といいます。
陰陽思想において金は「陰」、五行思想では「金」と「水」となり、常に流れ、とどまらないことを「吉」とします。
お金を増やしたいのであれば、このお金の性質が発揮される「循環」を意識することが大切です。
つまり、金運のめぐらせ方が鍵となります。
多くの方がお金持ちの「お金の稼ぎ方」を学びたいと思っていますが、中国では、お金の稼ぎ方よりもお金をどう使い、どう金運をめぐらせるのか、それを学ぶことを重要視するのです。ポイントとなるのが3つの力です。
1、発財力(はつざいりょく)…財を成して使う力
私たちがお金を稼ぎ、お金を使うことを表します。
お金を生み出して循環させられるかが金運を動かす、もっとも基本的な力となります。
お金を稼いで使うことは、自らの力で報酬を得ることであり、それが評価として認識されるので、充実感が生まれます。
2、蓄財力(ちくざいりょく)…財を貯める力
「備えあれば患(うれ)いなし」とも言うように、お金を蓄えることです。
稼いだお金を常に浪費し、手元にない状態では、自己投資の機会を逃したり、いざというときに困ってしまったりします。蓄財力は、安定力と同時に投資力に直結します。
そして貯金が増えると、安心感が生まれます。
3、招財力(しょうざいりょく)…財を引き寄せる力
他の2つの力と異なるのが、目に見えない力が関わっている点です。
お金は、他力によっても運ばれてくるものです。招財力が強い人には福の神が舞い込み、人とのご縁をつなげてくれます。
ご縁や運によって財や富がもたらされることで幸福感が生まれます。
「発財力、蓄財力、招財力」、この3つが揃うと、お金はどんどん増えていくでしょう。それと同時に、「充実感、安心感、幸福感」が揃うことで、物質的な豊かさだけでなく、心も満たされていくのです。
ここで注意したいのは、3つの力を強化する順番です。
多くの方がやりがちなのが、とにかく招財力を高めようと熱心に取り組むけれど、発財力、蓄財力への関心、取り組みはなおざりというパターン。
発財力があることによって、蓄財力が生じ、周囲の人や目に見えない力の応援によって招財力が高まり、お金の循環の法則は完璧な動きとなっていきます。招財力は、発財力、蓄財力があってこそ。注力するのは最後です。
また、3つの力のパワーバランスも重要です。
安心感を強く得たいという方は、発財力:蓄財力:招財力=5:3:2 にしてもいいでしょう。
ポイントは、ここでもまた招財力ばかりを強化しないこと。他力や運に頼ることも才ですが、神様にも、応援してくれた人にも、それ相応のお礼やお返しをしなければなりません。そのため、発財力、蓄財力が招財力よりも多くないと成り立たないということです。
この3つの力を備え、どんどん金運をめぐらせていきましょう!
【出典】『金運龍神風水』著:愛新覚羅ゆうはん
【書誌情報】
『金運龍神風水』
著:愛新覚羅ゆうはん
「投資ブームに乗っていない自分に焦るけど、なかなか勉強できない」「老後資金が足りるか心配でたまらない」「家計簿をつけるのが苦手すぎる…」
もし、そんな悩みを抱えているなら、節約よりも、投資よりも、まずは風水をおすすめしたい!というのが本書のメッセージです。
なぜなら…、
働いてもお金が貯まらない、漠然とお金の不安を抱えている、お金に向き合うことが苦手という人は、「環境」が雑然としていることが多く見受けられるから。
環境が整っていない=「場の気、ご自身の気が停滞している」という状態。
たとえ家計簿をつけても、投資を始めようとしても、お金はなかなか巡ってきてくれません。
風水は、掃除したり、片付けたり、色を意識したり…
何をしているかというと、環境に変化を与えることで、その環境が与える影響を「対策」しようという占いなのです。
言い換えれば、「停滞した運気と自分から脱出するメソッド=金運をつかむ最強の対策」。
しかも、日常生活を少し変えるだけ!という、お手軽さが魅力です。
本書は、2万5千人以上の鑑定実績を持ち、風水鑑定のもとすべての家選びをしてきた著者の実体験をもとに、効く「風水対策」を大公開。
占い業を通して出会ってきたお金持ちの方々から得た知見、「中国富裕層に伝わる常識」や「なぜかお金持ちに愛される龍神の秘密」、「運気向上を加速させる財運の3つの力」についてもお伝えしていきます。
・脱サラできるほど事業がうまくいった部屋とは?
・念願の書籍出版を叶えた風水対策とは?
・貯蓄額が一気に増えたインテリアと習慣とは? →気になる方は、ぜひ本書を!
この記事のCategory
求人情報
介護福祉士/介護職員・ヘルパー/有料老人ホーム/日勤のみ
ウェルビーナーシング株式会社ウェルビーメディハウス多々良
勤務地:福岡県 福岡市雇用形態:正社員給与:月給25万5,000円~スポンサー:求人ボックス
「電話受付スタッフ」「株価はどれくらいですか?」など問合せ 手当充実/証券外務員1種をお持ちの方
アルティウスリンク株式会社
勤務地:東京都雇用形態:給与:時給1,800円~2,050円スポンサー:求人ボックス
「経験必須」「Java/C++」「アーキテクト」商社向け グリーンフィールド導入の案件
株式会社コプロテクノロジー
勤務地:東京都雇用形態:業務委託給与:月給40万円~60万円スポンサー:求人ボックス
一般事務
株式会社ステップ・スリー
勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給23万5,000円~スポンサー:求人ボックス
電子機器のワイヤーハーネス加工エンジニア
株式会社SASAKI CONNECT
勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給22万円~28万円スポンサー:求人ボックス
SNS等で話題/人気ラーメン店の店長候補/26年5月に近隣へ新店舗オープン/未経験でも月給38万円~
株式会社エスジーカンパニー
勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給38万円~スポンサー:求人ボックス