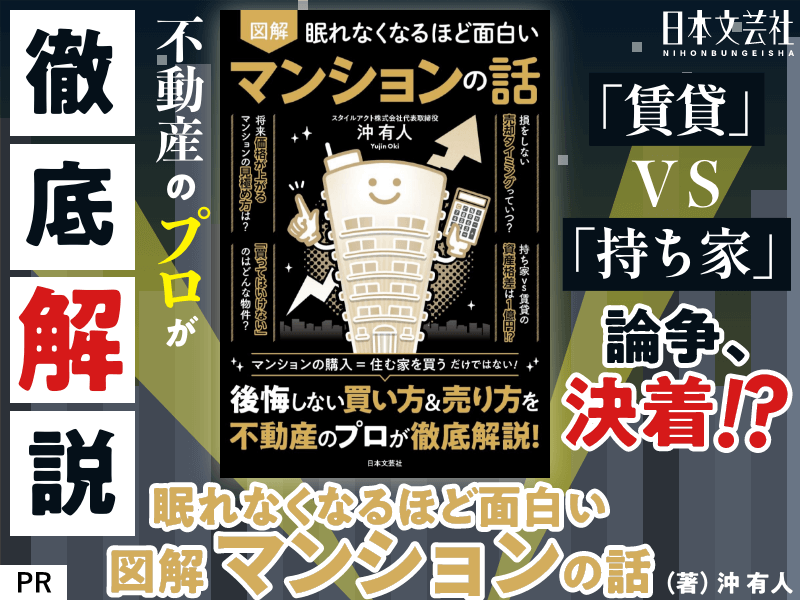ジェンダー、コロナ、そして東京2020。有森裕子「今、私たちが本当に考えなければならないこと」【緊急提言#1】


女性蔑視の発言で、東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森喜朗氏が会長の座を降りることとなった。偏見・差別のない平等はオリンピック精神の一つであるだけでなく、社会を織りなす根幹でもあり、一連の騒動は危機管理やガナバンスといった観点も含めて波紋を広げている。ジェンダー平等に賛同するHALF TIMEでは、マラソンのオリンピックメダリストであり、スペシャルオリンピックス日本理事長、国際オリンピック委員会(IOC)Sport and Active Society Commissionメンバーも務める有森裕子氏に、「緊急提言」を行っていただいた。
森喜朗元会長の発言に対する驚き
――まず東京オリンピック・パラリンピック組織委員会の森喜朗元会長の発言について、どんな印象を持たれたのか、お聞かせいただけますか。
「発言の内容に驚いたというよりも、今の世の中や時代の流れの中で、ああいう立場にある方が、そんな発言をしてしまうのかというのが率直な感想でしたね。
私はTwitter で『えっ?』と呟いたのですが、最初は情報が歪曲されて伝えられたり、一部だけ切り取られたりしたのかもしれないと思ったんです。だから改めて会見をすべて見直したんですが、あまり捻じ曲げられて報道されていたわけではなかった。その後の謝罪会見も踏まえて非常に残念に感じたというか、驚いたというか」
――日本の社会では昔から男女は違う、しかも女性は男性に一歩譲るべきだというような発想が根強く存在してきました。この種の状況は、あまり変わっていない印象を受けます。
「変わっていないんでしょうね。それに問題を解決していくために、男性女性を問わずに広く理解や共感を得ていく流れ自体が作れていない。むしろ関心のある人だけが騒いでいるというような捉え方をされてしまっている。
そもそも社会におけるジェンダーの問題は、まだまだ解決できていないじゃないですか。その点、スポーツは性別や世代、立場や障害のあるなしといった様々な違いを超えて、いろんな人たちを巻き込んでいくことができる。そして誰もが楽しく体を動かしたり、健康づくりをしたりしながら、社会に様々な問題があることを知り、それを解決していくための方法や人間社会にとって大切な『価値』を学んでいくことができる。
そういう社会的な意義を持っているからこそ、国連もIOCと連携してオリンピックを推進しているんです。ところがまさにオリンピックやパラリンピックを仕切る組織を束ねている立場の方が、ああいう発言をされてしまった」
女性差別問題と東京オリンピック・パラリンピック問題
――その後、後任に川淵三郎氏の名前が挙がり、次には川淵さんご自身が辞退されるという展開になったわけですが、今回の一件では、発言内容の良し悪しと、東京2020を開催すべきか否かという問題が一緒くたに論じられている印象を受けます。
「そう。東京大会をやるのかやらないのかという問題と、今回の発言の妥当性という問題はきちんと分けて考えなければならない。ところが実際にはそうはなっていない。
しっかり共感や理解を得ずして、大会を開催しようとするような姿勢も問題ですけど、今回の一件では、もともと開催に反対していた人たちが森さんの差別的な発言に便乗して、だから大会は開催すべきじゃないとさかんに主張するようになった。結果、大会の開催に反対しているのは、差別の問題に敏感になっている女性たちだけだと片付けられるような傾向も出てきてしまっている。これらの問題は本来、すべて別物なんです」
――そういう意味では、感情論的に反応してしまう側にも多分に問題がある。
「理由の一つは、やはり根本的なアプローチにもあったと思います。私は『初言・初動』という言葉をよく使うんですが、何かが起きてしまった時に、最初にどう動くか、どんなメッセージを発信するかというのはきわめて大切なんです。これはIOCもしかりです。
ところがIOCは森さんの発言が取り沙汰された時、まず『問題は解決済みだ』という声明を出し、今度はその5日後に『問題発言だった』という見解を示している。
普通に考えれば、順番は逆じゃないですか。実際にバッハ会長がどういう意図で声明を出したのかはわかりませんが、一連の報道を受けてIOCが最初に何を言うか、世の中に対してどんなメッセージをどう発信するかというのは、ものすごく大事だったんです。その点に関して言うと、余計に不信感と感情的な反応を招いてしまった側面は否めないですね」
危機管理と組織のガバナンス
――この問題には危機管理とガバナンスという、2つの要因があるような印象を受けます。まず現状をいかに正確に認識して、情報を発信していくかというノウハウが単純になかっただけでなく、一つの組織として自分たちの長がいかなるメッセージを発信すべきかというガバナンスが、徹底していなかったのではないでしょうか。
「結局、森さんにすべてを委ねなければ、動かないような組織になっていたということなんでしょうね。確かに識者の中には、森さんを弁護される方もいらっしゃる。森さんは7年間かけて様々な改革を行ってきたし、世界相手にいろいろと現場にコミットする数少ない人材だと。でも本来であれば、森さん以外にも優秀な人材がどんどん育っていて、組織の改革ができるような状況になっていなければならない。そういう組織づくりができていなかったという点での残念さはありますね」
――この種の問題も日本では根深いものがあります。日本社会は出る杭は打たれる式の文化が根強い。結果、一般企業でもあまり波風を立てず、そつなく日々の業務をこなし、自分の立場や役職、生活を守っていこうという発想の方が強くなる。
「どういう組織でも、そういう傾向は多少なりともあります。もしかすると今回のケースでも、森さんの周りには自分の立場を守るのに精一杯だった人たちがいたのかもしれない。でもJOCには、そういう発想をする人たちばかりがいるわけではない。自分なりになんとかして東京オリンピックやパラリンピックを成功させたい、すばらしい大会にしたいという熱意を持って、頑張っていらっしゃる方々もたくさんいるはずなんです。ただし実際には、いざという時に現場で森さんに代わろうとする人が登場してこなかった。その部分の問題が露呈したような気がしますね」
――結果、メッセージの発信の仕方も一方的になり、一般の方々の疑問や反感を招くようなものになってきてしまった。
「スポーツ界にいて組織の実情を知っている人や、森さんに近しい人たちは『いやいや、森さんはそんな方ではない。発言の真意はそこにはないし、世間一般の人たちがよくわかっていないだけだ』というような発言をされる。
でも、世間一般の人たちがスポーツ界の詳しい事情や、森さんのことを知らないのなんて当たり前じゃないですか。そもそもスポーツというのは、あくまでも社会の中にある一つのものであって、スポーツ界とは何の関係のない数多くの人たちに支えられている。そういう人たちに向けて、より理解や共感が得られるような発信をしていかないと何の意味もない。
逆にスポーツ界にしても、一般の人たちのことはよくわかっていないわけじゃないですか。『相手は何もわかっていない』とはねのけるのではなく、お互いに知らない者、わからない者同士が、相手に理解してもらう努力をしていくのが大切なんですよ」
SDGsのスローガンに見る皮肉
――相互理解を深めていく上では、まずは男女が性別を超えて問題に向き合っていくことが必要になります。男性は女性差別の問題にどう向き合うべきでしょうか。
「スポーツは、社会にいろいろ変化や改革を促していける最高の手段なんですが、日本の場合はその現場の大半を男性が占めている。昔に比べれば状況は少しずつ変わってきたと思いますが、結果、いまだに男女の格差という問題を取り上げなければならない。
これはSDGs(持続可能な成長)の問題によく似ているんです。日本では東京オリンピックやパラリンピックの一つのスローガンに位置付けられ、関係者の方がSDGsのバッジをつけるようになった。でも、あんなことをしているのは日本だけなんです。むしろ海外では、SDGsについて考えられることが当たり前になっていますから」
――仰っていることはよくわかります。「女性差別」という単語が存在すること自体、依然として問題が解消されていないということに他なりませんから。一方、女性はこの問題をどう捉えるべきでしょうか?
「例えば能力の同じ男性と女性が、職場で同じチャンスを与えられたとします。こういう場合、男性の方が圧倒的にチャンスをつかもうとするし、つかめる立場にもなるでしょう。逆に女性はサポートも含めて、チャンスをつかめるような環境が簡単には与えられない。この差がある限り、女性はなかなか目の前にあるチャンスをつかもうとしない。チャンスがあっても尻込みしたり、私はそれでいいと甘んじてしまったりする人も少なくないでしょうし」
――ただし機会均等の問題に関しては、女性は出産や子育てを優先すべきだという発想が、男女を問わず昔から根強かったのも事実です。これもまた少なからず、影響を及ぼしてきたのではないでしょうか。
「そうですね。その発想から抜け出せなかったり、変えにくかったりする。ましてや、周りから理解が得られないことに対する不安が消えないのは確かだと思います」
女性にとって真の建設的な議論とは
――今回の一連の議論では、女性の方が女性の識者の論調に温度差を感じるという現象も起きています。むろん男女格差の問題は厳然として存在していますし、社会全体として真摯に取り組んでいかなければならない。とは言え女性の識者の方が、あまりに急進的な立場を取ったり、男性vs女性という視点ばかりで問題を捉えられるのも、あまり建設的ではないという印象を受けます。この点についてはいかがですか?
「ええ、全然、建設的じゃないと思います。簡単に言えば、そういう捉え方や情報発信の仕方では問題解決に至らないと思いますから。男女差別の問題の場合、ともすれば『敵は男性だ』という発想になりがちだし、そこを基準に見えない壁と戦っていこうとしてしまう。でもそこが問題の本質ではないし、私たち女性は女性のために、女性差別の問題を考えていますというようなスタンスを前面に押し出すと、『言いたいことはわかるんだけど、ちょっと待ってよ」と思うような男性を増やしてしまうことにもなる。
むしろ男女格差という問題というのは、男性か女性かではなく、もっと社会的な問題、人間とヒューマンライツ(基本的人権)の問題として考えていかないダメなんです。当然、男性も当たり前のように議論に入ってこなければなりませんし。私は国連人口基金(UNFPA)の親善大使をやった時に、その必要性を痛感しましたね」
「ウィメンズ・ライツ」ではなく「ヒューマン・ライツ」を
――日本の状況を変えていくためには文化論云々ではなくて、人権論や理念論に踏み入っていかなければならない。
「そう思います。もちろん男女差別で嫌な思いをしたり、散々な目に遭っている方は山程いますし、私自身、今起きている問題を軽視するつもりはまったくない。例えば政治家の方が女性議員という言葉を口にしたら、『いや、男性議員という言葉はありませんよね?』とすぐに指摘していかなければならない。政治家には男性も女性も関係ないからです。
でも、そういう問題を解決するためにも、女性は女性の立場から『ウィメンズ・ライツ』を主張するのではなく、一人の人間として『ヒューマン・ライツ』を訴えていく。その上で、男女それぞれが持つ特性をいかに理解していくかという視点に立たないと、そろそろ限界にきているんじゃないかと思いますね。従来の発想では、男女差別はいつまで経っても特殊な問題としてしか受け止めてもらえませんから」
聞き手:田邊 雅之
学生時代から『Number』をはじめとして様々な雑誌・書籍でフリーランスライターとして活動を始めた後、2000年から同誌編集部に所属。ライター、翻訳家、編集者として多数の記事を手掛ける。W杯南アフリカ大会の後に再びフリーランスとして独立。スポーツを中心に、執筆・編集活動を行う。
初出=「HALF TIMEマガジン」21年2月18日掲載
スポーツビジネス専門メディア「HALF TIMEマガジン」では、スポーツのビジネス・社会活動に関する独自のインタビュー、国内外の最新ニュース、識者のコラムをお届けしています。
この記事のCategory
オススメ記事

「ママチーム」スウェーデン代表の衝撃と、地元チーム創立から10年。本橋麻里が掲げる「次の夢」

Jクラブの「地元ファン」をどのように定量化して捉えるか?【データで語ろう#1】

「ガバナンスと持続性で世界最高峰リーグに」葦原一正代表理事が語る、日本ハンドボールリーグの挑戦

J福島ユナイテッドの調査から考える、ファンの「構造化」【データで語ろう#2】

HALF TIMEカンファレンス、2021年の第一弾開催が決定。コロナ禍での 「DX」最前線とは

日本ラグビーフットボール協会、ヒト・コミュニケーションズとのスポンサー契約を締結

【データで語ろう#3】福島ユナイテッドの魅力を高める要素とは?

TOKYO DIME「一人目社員」の八木亜樹さんに聞くキャリア。転職、上京、大手生保から「バスケの営業」に
求人情報
機械装置の組立/アッセンブリ/スタッフ
株式会社アイ・エム・ジー
勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給20万円~27万円スポンサー:求人ボックス
住宅型有料老人ホームの施設長/上場企業グループ/月平均残業10h・ 2025年5月オープン・介護業務なし
ユアスマイル株式会社 ライフパートナー交野
勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給32万円~スポンサー:求人ボックス
イタリアンの調理スタッフ/経験者募集!高収入 あなたのアイデアが人気メニューに
株式会社ジャックポットプランニング
勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給28万5,900円~42万7,600円スポンサー:求人ボックス
ガス給湯器等の取付・交換
株式会社キンライサー 東東京サービスセンター
勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給35万円スポンサー:求人ボックス
40~50代活躍中!東急グループの安定基盤で働く施設警備/未経験歓迎
東急セキュリティ株式会社
勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給25万8,231円~30万円スポンサー:求人ボックス
パチンコ店のホール・フロアスタッフ/月給30万円
株式会社喜久家
勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給30万円~スポンサー:求人ボックス