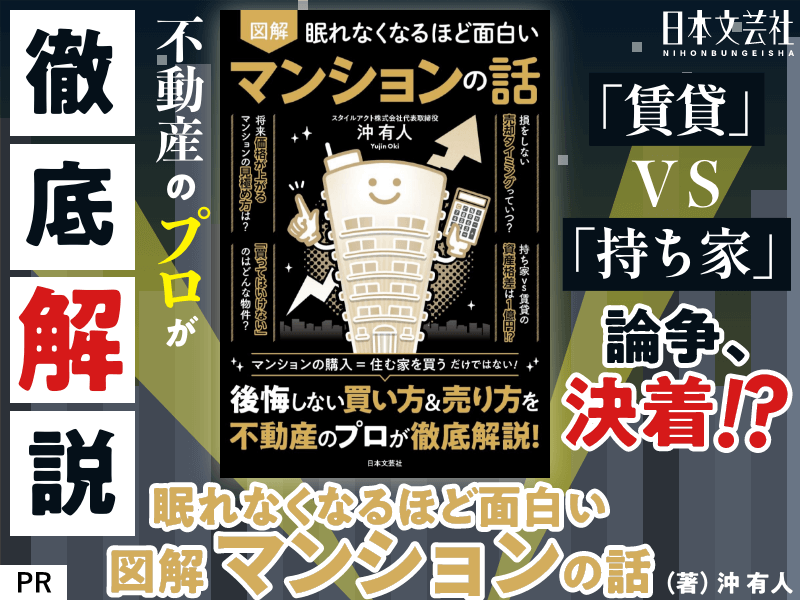【東京2020】国際広報としての挑戦と、大会の「忘れ物」(小倉大地雄氏)


スポーツビジネスの現場リーダーに、これまでのキャリアと現職について伺う連載企画。今回は、今月閉会を迎えた東京オリンピック・パラリンピックにあわせ、東京2020組織委員会の国際広報担当課長 小倉大地雄(おぐら・たつお)さんに伺いました。(聞き手はHALF TIME編集部 横井良昭)
東京2020を海外へ発信する国際広報
――まず初めに、小倉さんの現職について聞かせてください。五輪の広報、それも海外向けというのはどういった仕事なのでしょうか。
私が今いるのは、東京2020組織委員会の広報局広報部、そこで国際広報を担当しています。日本の組織にいると海外に向けた発信を行う機会は少ないですが、オリンピック・パラリンピックなどの世界的なイベントでは海外への発信やコミュニケーションが重要になります。
国際広報で重要な職務のひとつは、国際メディアへの対応です。ロイターやAP、AFPなどの通信社、またニューヨークタイムズ、ガーディアンなどの新聞社、NBCやBBCなどのテレビ局からの問合せや取材への対応をチームで行っています。海外メディアからの注目度も高く、平昌2018大会が終わった頃から問い合わせが増え、特に大会1年前を切ってからは劇的に増えました。また積極的なニュース創出と組織としての透明性の担保のため、プレスリリースを配信するなどの業務を行っています。
コミュニケーションをとるステークホルダーが多いのも特徴です。国際オリンピック委員会(IOC)と国際パラリンピック委員会(IPC)という主催者はもちろん、競技を運営するIF(International Federation:国際競技連盟)や各国のオリンピック委員会・パラリンピック委員会、IOCのトップパートナーを含むマーケティングパートナー、そして開催都市である東京都や日本政府・各行政機関など本当に多岐にわたります。
――どのようなチームでこれまで準備されてきたのですか?
私は国際広報チームの3人目のメンバーとして2016年のリオ五輪前に着任しました。大会1年前までは国内メディアの対応が中心になるため、国際広報のメンバーは少人数で活動をしていました。しかし大会に近づくにつれて海外との対応が増えます。最終的には、国際広報だけで20人にもなりました。組織委員会は2014年に立ち上がり、今年で7年が経過しました。徐々に国内広報と国際広報のバランスが変わっていく、不思議な現場でしたね。
水泳をきっかけにスポーツマネジメントの道へ
――小倉さんのこれまでのキャリアを教えてください。
3歳から大学までは水泳をしていました。でも大学時代、競技成績はたいしたことなくて(笑)、大学1年の時のインカレではレギュラーに選出されなかった。その時からマネージャーや高校生のスカウティングに関わるようになり、選手データの収集や分析に興味を持ちました。
その後アメリカの大学院でスポーツマネジメントを学ぶ事になりますが、きっかけは早稲田大学在学中に、スポーツマネージメント学科ができたことです。そこで、スポーツマネジメントという学問の存在を知りました。当時の水泳界はプロという道がまだ広く開かれておらず、選手がどのようにプロアスリートとして生活していけるかを考えたかったんです。留学中には現地のスポーツマーケティング会社でインターンも経験しました。
――大学院卒業後は、いかがでしたか。
2008年に帰国したんですが、当時は北島康介選手が北京五輪で平泳ぎ2種目2連覇を達成したことで競泳への注目度も高まっていました。それに、北島選手の指導をしていた平井伯昌コーチが日本代表ヘッドコーチに就任するタイミングでもあったんです。平井コーチは大学の先輩ですから連絡をしたところ、「いいタイミングで帰ってきた」と(笑)。
実は、次の五輪(2012年ロンドン)でのメダル獲得の有力種目を対象に医科学のサポートを行う「チームニッポン・マルチサポート事業」が始まっていて、競泳もその一つだったんです。そうして日本代表チームのサポートスタッフの打診をいただいて、日本での最初のキャリアが始まりました。
ロンドンまでの契約でしたが、ファーストキャリアとしてスポーツ組織の中に入ることは大事だと思って、参画しました。帰国した当初はマーケットがすでに大きなプロ野球やJリーグでの仕事をイメージしていて、水泳に携わる仕事は将来的にと考えていたんですけどね。その後、日本水泳連盟からロンドン五輪後も何らかの形でチームに残ってほしいとオファーをいただき、2013年からリオ五輪に向けて、連盟所属で日本代表チーム広報に就くことになったんです。
――その後現職へ転職されることになります。どのような経緯だったのでしょうか?
きっかけは、組織委員会でスポークスパーソンを務める高谷正哲さんから声をかけていただいたことです。ただ当初は、「リオ五輪が終わるまで競泳代表チームを離れるのは難しい」と伝え、リオ大会後に転職するつもりでした。しかし、その後組織委員会側の事情もあって再び連絡をいただいたのですが、1週間で結論を出さないといけない状況になり(苦笑)、「いまこのタイミングで話を蹴ったら、もしかしたら組織委員会の仕事はないかもしれない」と考えて決断しました。
所属していた競泳日本代表チームの平井コーチなど、お世話になった方々にも相談すると、「水泳界からそういう世界に行く人間がいるのも重要だから、水泳界のためにもぜひ頑張ってくれ」と快く送り出していただいて。そして2016年リオ五輪代表選考会が終わった後、5月より組織委員会で働き始めました。
競技外の部分で「忘れ物」

――先日、パラリンピックも閉幕を迎えました。広報の現場はいかがでしたか。
国際広報として難しかったのは、国内メディアでは組織委員会の担当記者が日々情報を追いかけますが、海外メディアの東京特派員たちは必ずしもそうではないことでした。東京2020大会だけを追いかけているわけではないので、拾いきれない情報もあります。我々のチームがいかにそういった方に情報を補って発信してあげられるか、取材の機会を設けられるかというのは苦労した部分でした。
良かった点は、チーム内に多様で優秀な人材が揃っている所だと思います。外国人のスタッフはもちろん、スポーツ界、自治体、メディア、企業広報経験のある多様な方々在籍しているので、それぞれの個性を活かした配置などでチーム力を高められたことが僕自身としても貴重な経験でした。
――米国留学から水泳の日本代表チーム・連盟まで。これまでの経験から現職に活きたことは。
オリンピック・パラリンピックは特殊で、専門用語も多く特有のレギュレーションも存在します。なので、自分自身が日本代表のスタッフとしてロンドン五輪に行った経験が活きました。五輪という環境を経験したことで、大会時にどんな場所でどんなことが起きるか想像することができました。
あとはやはり語学力ですね。英語力が最低限備わっていないと海外のステークホルダーとのコミュニケーションは取れませんし、通訳・翻訳があるといってもひとつひとつの仕事で入れるわけにもいきません。語学力があるのとないのでは大きな差があると日々の業務の中でも感じました。
――最後に、今大会を振り返りつつ、小倉さんの今後に向けた抱負があれば教えてください。
多くの方がそうかもしれませんが、この東京オリンピック・パラリンピックで、日本中、世界中の方々に体感してほしかったことが100%できたのかと問われると、必ずしもそうではありません。
本来であれば競技を観て楽しむだけでなく、各国の文化的な側面の発信やパートナー企業による盛大なプロモーション、そして市民と選手などの交流が行われ 、街中がオリンピック・パラリンピックムードに包まれていたと思います。過去の大会でそうした雰囲気を感じた身としては、東京大会でも同じように体験してほしかったという、やり切れなさが残りますね。
もちろん、選手たちの活躍で日本中が盛り上がったとは思います。ただ、自分の中では、競技外の部分で「忘れ物」があるので、オリンピック・パラリンピックは終わりましたが、少しでも本来の空気を体験してもらえるような取り組みをしていきたいですね。
初出=「HALF TIMEマガジン」9月22日掲載
スポーツビジネス専門メディア「HALF TIMEマガジン」では、スポーツのビジネス・社会活動に関する独自のインタビュー、国内外の最新ニュース、識者のコラムをお届けしています。
この記事のCategory
オススメ記事

「なぜ日本はオリンピック一択?」 カーリング本橋麻里が国際舞台で感じた、価値観の違いと真のダイバーシティ

「ガバナンスと持続性で世界最高峰リーグに」葦原一正代表理事が語る、日本ハンドボールリーグの挑戦

「リーグ上位・売上下位」を変えていく――。サンフレッチェ広島 営業部の悦喜裕也氏が地元クラブで挑むこと【30代キャリア】

【データで語ろう#3】福島ユナイテッドの魅力を高める要素とは?

2020年版「好きなスポーツ選手ランキング」が発表。羽生結弦が前回に続き第1位、大坂なおみが4位に躍進

35歳でスペイン移籍。サッカー元日本代表 丹羽大輝を支えた「準備力」

HALF TIMEカンファレンス、2021年の第一弾開催が決定。コロナ禍での 「DX」最前線とは