戦国武将の話

太田道灌は、なぜ主君によって殺されたのか?【戦国武将の話】
器量の小さい主君に優秀さを危険視された 室町幕府は関東統治の出先として、足利一門から鎌倉公方(くぼう)を選び、その補佐役である関東管領には重臣の上杉氏をあてがった。 関東では畿内より一足早く秩序が乱れ始め、15世紀後半に […]

六角定頼は、先見性が高い武将といわれる理由は?【戦国武将の話】
織田信長より28年も前に楽市を実施 六角(ろっかく)氏は近江源氏の血を引く由緒ある名門の出身。源頼朝(みなもとのよりとも)の挙兵に参加した佐々木四兄弟の一人、定綱(さだつな)の後裔(こうえい)である。定綱の子信綱(のぶつ […]

大内義興は、なぜ異国の町で細川氏と事を構えたのか?【戦国武将の話】
日明貿易による莫大な利権を争って 応仁・文明の乱の序盤は東軍が優位に進めていたが、西国からの援軍の到来にともない西軍が盛り返し、ほぼ互角の形勢となった。この援軍のなかでも周防(すおう)の大内政弘(おおうちまさひろ)の存在 […]

朝倉孝景は、なぜ東軍に寝返ったのか?【戦国武将の話】
守護と守護代を破り、家老から戦国大名へ 戦乱長期化の最大の要因は戦力の拮抗にある。東軍としては、瀬戸内海の制海権を巡り、細川勝元と競合関係にある大内政弘(まさひろ)は無理でも、朝倉孝景(あさくらたかかげ)なら寝返る可能性 […]
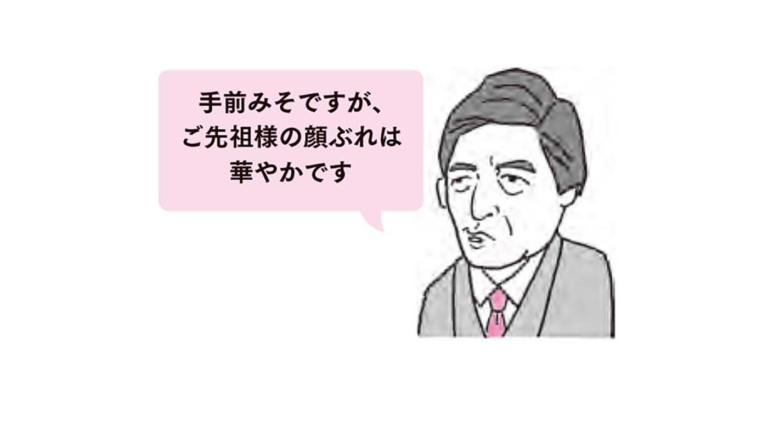
細川政元の戦国史上、類を見ない個性とは?【戦国武将の話】
性的嗜好と信仰を優先し、務めを放棄 細川氏は足利氏の一門。政元(まさもと)は東軍総大将を務めた細川勝元の嫡男(ちゃくなん)で、惣領家(そうりょうけ)である細川京兆家(けいちょうけ)の家督をも継承した。 応仁・文明の乱は終 […]

山名宗全は、応仁・文明の乱の終わりを見ずに隠居?【戦国武将の話】
責任感の強さゆえに精神を病んだ 応仁・明の乱をとことん単純化すると、対立の当事者は東軍総大将の細川勝元(かつもと)と西軍総大将の山名宗全(やまなそうぜん)の2人といえる。細川氏が幕府を支える三管領の一つなら、山名氏も同じ […]

足利義政は日本史上、屈指の暗君だった?【戦国武将の話】
無定見かつ無責任極まりない暗君 15代まで続いた点は同じでも、江戸時代の徳川将軍と比較すると、室町時代の足利(あしかが)将軍の影はやはり薄い。そのなかにあって、室町幕府の8代将軍足利義政(よしまさ)は比較的知名度の高いほ […]
