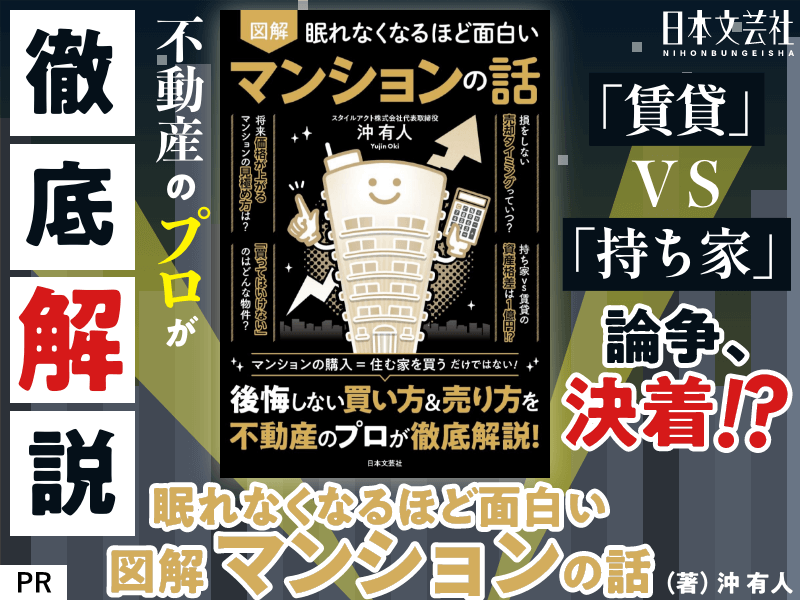50年前のセンバツ。池田イレブン旋風【二宮清純 スポーツの嵐】


“攻めダルマ”もうひとつの顔
今なら「それはサッカーのチームですか?」と首をかしげられるかもしれない。
今から半世紀前、1974年春の甲子園は、四国の山間(やまあい)のまちからやってきた池田(徳島)が大旋風を巻き起こした。
わずか11人の部員ながら、あれよあれよという間に勝ち進み、準優勝を果たしたのだ。
その戦いぶりが爽快感あふれるものだったため、選手たちは“さわやかイレブン”と呼ばれた。
当時のベンチ枠は14人。甲子園に出場するような強豪校なら、ベンチ入りメンバーを絞り込むのにひと苦労するところだが、池田は3人も余して5試合を戦い抜いた。
後に“山びこ打線”と呼ばれる強打で、甲子園を3度(82年夏、83年春、86年春)制した池田だが、この頃は少ない得点をひとりのピッチャーが守り切る、実に高校生らしいチームだった。
というのも、この年の夏からバットが木製から金属製に切り替わった。すなわち74年のセンバツは木製バットが使用された最後の大会だった。
蛇足だが、高野連が金属バットを導入した最大の理由は、73年に発生したオイルショックだった。全国のスーパーマーケットからトイレットペーパーが消えたことを知る者も、最近ではだいぶ少なくなってきた。
原油価格の引き上げにより物価が高騰した。当時の通産大臣・中曽根康弘は、供給の途絶を懸念して国民に紙の節約を呼びかけた。
これを国民は「紙がなくなる」と早合点した。トイレットペーパーが不足すれば、安心して用も足せない。こうした国民の不安につけ込むように、買いだめに走る悪徳業者が続出した。コロナ禍のマスク不足も、これに似ていた。
木材価格も急騰した。スポーツ用品店に陳列されていたバットの値段は一気に倍にはね上がった。現場の悲鳴を、高野連は無視することができなかった。
さて、池田の決勝までの勝ち上がりを見てみよう。1回戦4対2(函館有斗・現函館大有斗=北海道)、2回戦3対1(防府商=山口)、準々決勝2対1(倉敷工=岡山)、準決勝2対0(和歌山工)。決勝こそ報徳学園(兵庫)に1対3と競り負けたが、どの試合もクロスゲームである。
80年代、金属バットの特性を最大限利用した超攻撃野球で名を成す蔦文也監督だが、この頃は本盗、重盗、エンドランなどの機動力を駆使して1点をもぎ取っていた。“攻めダルマ”と呼ばれた男の、もうひとつの顔である。
初出=週刊漫画ゴラク2024年3月22日発売号
この記事のCategory
オススメ記事
求人情報
一般事務
株式会社ステップ・スリー
勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給23万5,000円~スポンサー:求人ボックス
オーガニックカフェのホール・キッチンスタッフ/週2日から勤務OK/未経験歓迎/学生・フリーター活躍中
株式会社ウカ
勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,250円~スポンサー:求人ボックス
交通誘導警備員/夜勤/日払いOK/週休2日 未経験者歓迎
株式会社NAKASU
勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:日給1万6,760円スポンサー:求人ボックス
2トンドライバー×正社員×渋谷区
株式会社三祐商会
勤務地:東京都雇用形態:給与:日給8,000円スポンサー:求人ボックス
化粧品会社のEC運営・企画・マーケティング
クー・インターナショナル株式会社
勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給26万円~スポンサー:求人ボックス
調剤薬局の薬剤師
イオンスタイル板橋前野町
勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:時給2,650円~2,920円スポンサー:求人ボックス