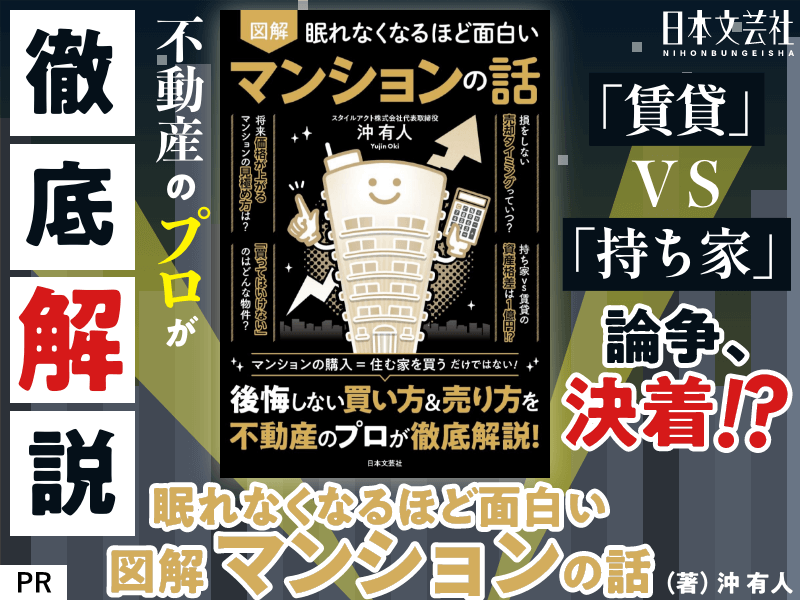第5回 オカダ・カズチカがAEWのトップレスラーとして、さらに認められるために突きつけられる”プロモの高い壁”とは!?



”チームユニットであるThe Eliteから最高級のスポーツカーをサプライズでプレゼントされ、涙を浮かべて喜ぶオカダ・カズチカ。新日本時代の絶対的王者の雰囲気から一転、コミカルキャラを満喫しているが・・・。 – 2024年5月29日(現地時間)カリフォルニア州ロサンゼルス キア・フォーラム –
2024年3月、退団した新日本プロレス(以下、新日本)から電撃的にAEWへと移籍を果たしたオカダ・カズチカ。日本のトップレスラーの登場に、ファンにも大いに歓迎されたオカダではあったが、その後はどういった活躍を見せているのだろうか。
オカダは、新日本所属時代「ヒールのように強いベビーフェイス」という立ち位置で、圧倒的な強さを持ち味としたレスラーとして君臨した。現に同団体の象徴であるIWGP世界王座ベルトを幾度も戴冠したことからしても、実力は折り紙付きだ。AEWでも同じくその強さを信条にしたベビーフェイスのキャラクターとして立ち振る舞うかと思われたが、意外にも一転してヒールキャラへと立ち位置を変え、今や登場すれば会場からのブーイングを浴びるという立派な”悪役”を演じている。
この予想外の”ヒールターン”はインパクトの強さから、極めて好意的に受け止められたように思われるのだが(ヒールが好意的というのは、いささか不思議な言い回しではあるが)、ここ数ヶ月に渡るオカダの姿をつぶさに見るにつけ、一抹の物足りなさを感じているのも、また事実だ。
オカダは新日本に”レインメーカー”の異名で凱旋する以前に、海外武者修行と称して米プロレス団体であるTNAのリングで活動していた。そこで交友を深めた、今はAEWの副社長の兄弟タッグチーム、ヤング・バックスが率いるユニット”ジ・エリート”で彼らと行動を共にしている。ジ・エリートは副社長の立場を利用して、マッチメイクや対戦内容はおろか、団体の人事なども勝手に取り仕切り、リング内外で傍若無人な振る舞いを見せており、その無法ぶりは凄まじい。オカダはいわば、ヤング・バックスの二人によって新たにAEWに招聘された、旧知の日本人レスラーという立ち位置なのだ。
悪役として活動するには極めて都合のいいポジションというべきだが、そんなオカダにとって完全なヒールを名乗るには、「悪役ユニットに所属した」というだけでは到底おぼつかない、アメプロ特有の大きな壁が立ち塞がっているように、筆者には思えてならない。それはズバリ”プロモ”の存在だ。
プロモとは、文字通りプロモーション=宣伝の意味だが、アメプロにおけるプロモとなると、試合は行わずにマイクを手にリングに上がり、侮辱的な言葉や侮蔑する表現を用いて、敵対する者同士の因縁や確執を、観客や視聴者に分かりやすく”言葉”で伝えるためのギミックのこと。その形式は様々で、リング上でのパフォ―マンスや別ロケーションで収録されたビデオ形式など、アメリカならではのスケール感が展開する内容も決して珍しくない。こうしたギミックを通して、やがて行われる実際の試合に行きつくまでのストーリーの良しあしが、最終的な試合の注目度を決めるといっても過言ではないほどに、プロモは極めて重要な役割を占める要素なのである。

海外経験も極めて豊富なオカダが、英語をまったく介さずに喋ることができないなどということは、事実としてあり得ないことだ。過酷な海外でのレスラー生活を若手時代から長年経験しているわけでもあり、日常会話はおろか団体を運営するプロモーターなどとも契約や日々の意思疎通など、最低限のやりとりをしなければならないシチュエーションは数多くあることは想像に難くない。
ましてや専属の通訳などいない状況で、オカダの英語力はかなりのレベルにまで上達しているはずである。しかしながら、現在のオカダのキャラクターは「試合はできるが、英語は喋れない日本人」という枠に押し込められている。もしこれが意図的に狙ったギミックなのであれば、残念ながらそのストーリーギミックは失敗していると言えはしまいか。それは会場にいる観客の、少々醒めた感じの反応を見ても明らかだ。
現在のオカダは、プロモで英語を使わないおかげで、どうにもおバカキャラ的な役割を担わされてるように思えてならない。もちろん試合をすれば、その実力は今更証明して見せる必要もないほどの高みに達しているわけだが、そんなオカダがプロモでは、ヤング・バックスからサプライズ・プレゼントとして贈られた最高級のスポーツカーを目にして、観客の前で涙を浮かべて感激しながら、「オーマイガ!オーマイガ!」と連呼したりしているのだ。この惨状ともいうべき状況に、底知れない危惧と深い落胆を感じているのは、果たして筆者だけだろうか。
AEW登場時のまさかのヒールターンの衝撃さながらに、突如プロモを完璧にこなすようになるという”第二のレインメーカーショック”が、今後のオカダのストーリーとしてしっかりと用意されているであろうことを、ファンの一人として切に願わずにはいられないのである。
この記事のCategory
オススメ記事

9月30日(月)19:00~開催決定・田辺裕信騎手トークショー&BINGO大会【日本中央競馬会(JRA)所属ジョッキー】

第4回 特別企画・緊急帰国! AEW中澤マイケル直撃インタビュー

第3回 満を持してG1クライマックス参戦を果たしたAEWの大器、”竹下幸之介”に刮目せよ!

第2回 AEWは女子も熱い!天才的格闘センスの持ち主にしてマルチな才能を発揮する"レディ・サムライ”志田光

第1回 MLB大谷翔平だけじゃない!メジャーで夢を叶える日本人プロレスラー”オカダ・カズチカ”

G馬場とプロレス 。「大男」のリベンジ【二宮清純 スポーツの嵐】

64代横綱・曙死す。なぜ力士は短命か【二宮清純 スポーツの嵐】

76年アリの真実。猪木戦の舞台裏【二宮清純 スポーツの嵐】
求人情報
施工管理
株式会社イチグミ
勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:年収600万円~960万円スポンサー:求人ボックス
新築解体現場作業員/未経験者歓迎 高日給×日払い×ミニボーナスの高待遇
株式会社SK総業
勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:日給1万3,000円~1万7,000円スポンサー:求人ボックス
スーパーのオープニングスタッフ
コープ津久野店
勤務地:大阪府雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,180円~スポンサー:求人ボックス
昼勤専属/1日6時間/セルフSSモニター監視スタッフ/危険物乙四免状必須
株式会社大栄舎
勤務地:愛知県雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,140円スポンサー:求人ボックス
既存顧客向けのルート営業/土日祝休み×ノルマなし!未経験OK!売るより信頼を築く営業へ
AFS株式会社
勤務地:愛知県雇用形態:契約社員給与:月給24万円~スポンサー:求人ボックス
一般事務/20代活躍中/完全週休二日制/土日休み
株式会社スリーヴイアメニティ
勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給23万円~26万9,000円スポンサー:求人ボックス