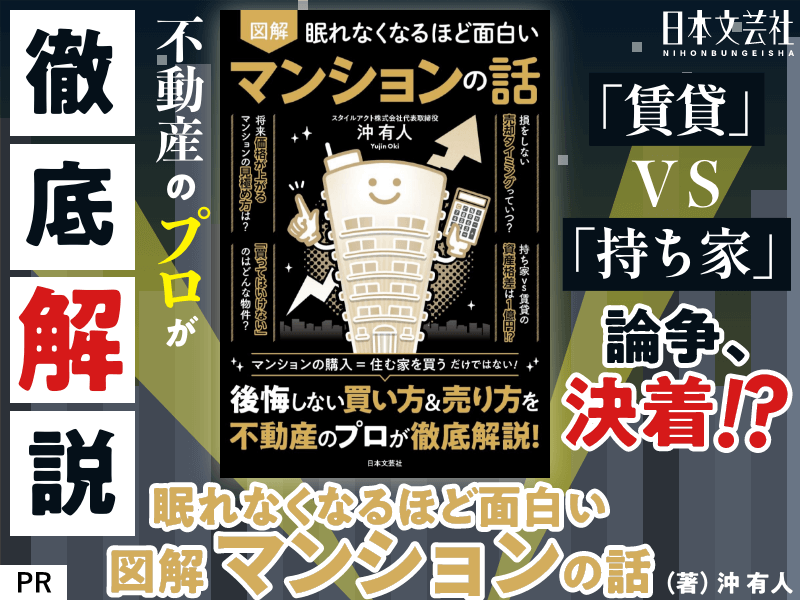長嶋茂雄「天才伝」。“悪球打ち”の真実【二宮清純 スポーツの嵐】


バットの届く範囲の球は打てる
プロ野球を超えた国民的ヒーロー・長嶋茂雄の訃報に接したイチローは共同通信に次のようなコメントを寄せた。
「理屈ではなくフィーリングでプレーする方。天才とはこういう選手のことを言うのだ、と感じた。憧れの対象であることをご自身でも理解され、憧れられる立ち居振る舞いとは何なのか、をとことん追求され、完璧に表現された方だったのではないでしょうか」
長嶋と日米通算4367安打のイチローには共通点がある。それはストライクゾーンに対する認識だろう。
イチローは、日米を通じてよく、本塁のベース板の前でワンバウンドしたボール球に手を出し、ヒットにしていた。あたかもテニスのラケットで打ち返すような卓抜のバットコントロール技術がそれを可能にしたのだ。
自分が打てると思ったボールがストライク。イチローは、そう考えていたのではないか。
しかし“悪球打ち”に関しては、長嶋の右に出る者はいない。
古い話で恐縮だが、1960年7月17日、川崎球場での大洋(現横浜DeNA)とのダブルヘッダー第1戦。サウスポー鈴木隆の敬遠気味の内角高めの真っすぐを、大根切りでレフトオーバーに2点ランニング本塁打を放っている。
レフトの沖山光利が太陽光の中でボールを見失ったという逸話が残っている。まさか長嶋が打ってくるとは……。虚を突かれたのかもしれない。
長嶋の自著『ネバーギブアップ』(集英社)に、“ボール打ちの名人”に関するくだりがある。
<「顎の辺りを通過する球を大根切りで打っておいて、ボールを打たないもないもんだ」と思う人がいるかも知れないが、あれは、私にとってボールではない。ストライクなのである>
ストライクかボールかを判断するのは、言うまでもなく審判だが、長嶋は<打者がそのストライクゾーンを踏襲しなければならない理由はない>と喝破する。
そして、こう結ぶ。
<つまり、打つ気さえあれば、バットの届く範囲の球は打てるのである>
好球必打。これが打撃の王道である。好球がボール球であるはずがない。
ところが長嶋は、そしてイチローは、自分が打てると判断したボールが、いわゆるストライクなのである。“悪球必打”とまでは言わないが、勝負する相手はストライクゾーンを司る審判ではなく、あくまでも相手投手なのだ。
天才の思考は、天才にしか理解できないということか。
初出=週刊漫画ゴラク2025年7月4日発売号
この記事のCategory
オススメ記事
求人情報
新聞販売店でのエリアマネージャー
朝日新聞サービスアンカー ASA吹田
勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給25万円~スポンサー:求人ボックス
普通免許から始める路線バスドライバー
西東京バス株式会社
勤務地:東京都雇用形態:正社員給与:月給21万5,000円スポンサー:求人ボックス
直行直帰OK/中学受験/国語・社会のプロ家庭教師/初仕事ボーナス3万円
株式会社イスト
勤務地:東京都雇用形態:業務委託給与:時給3,000円~1万円スポンサー:求人ボックス
ラインリーダー候補/日勤のみ/家具家電付1R寮・寮費光熱費一部負担/土日休みで年間120日以上
株式会社ミックコントラクトサービス
勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給24万5,071円~スポンサー:求人ボックス
神戸ハーバーランドumieの設備管理スタッフ
神戸ダイヤメンテナンス株式会社
勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給21万8,900円~スポンサー:求人ボックス
Amazonオフィシャル配送サービスパートナー/軽貨物ドライバー
株式会社Blanc
勤務地:東京都雇用形態:業務委託給与:日給2万2,850円~2万9,450円スポンサー:求人ボックス