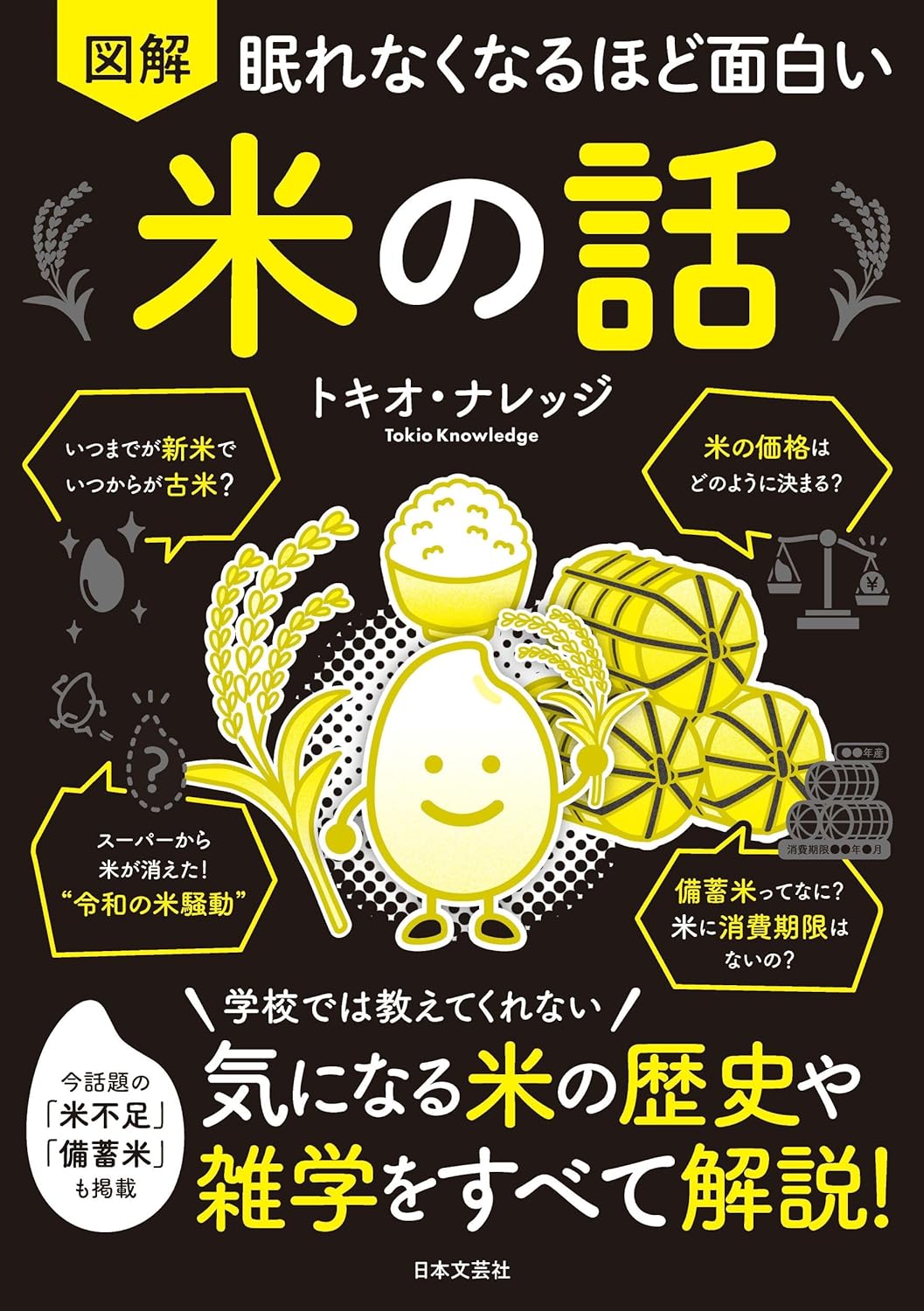大正の暴動、平成のタイ米、令和の買い占め…繰り返される「米騒動」の歴史とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】


米騒動は過去に何度も起こっている
大正・昭和・平成に続いた波乱
米が足りない、価格が高騰する、買いたくても買えない─そんな「米騒動」は、令和にはじまったわけではありません。日本の歴史において、米をめぐる混乱は何度も繰り返し生じてきました。
その象徴的な出来事が、1918年(大正7年)の「大正の米騒動」です。富山県の漁村で米価の高騰に抗議した主婦たちの声が全国へ広がり、打ちこわしや暴動が続発。政府が軍を出動させる騒ぎとなり、最終的には内閣総辞職にまでいたる国家的事件へと発展しました。
続く昭和の戦中・戦後には、米は配給制となったことで「ヤミ米」が横行。国民の食を支えるべき制度に不信が広がるだけでなく、都市と農村の間で流通の格差も深まり、人々の暮らしに大きな影を落としました。
さらに1993年(平成5年)には、記録的冷夏により「平成の米騒動」が発生。収穫量が激減し、スーパーから米が消える異常事態に。政府はタイ米などを緊急輸入しましたが、細長く香りの強い外国米に戸惑う声が相次ぎ、食卓にも混乱が広がりました。
そして令和の時代に起きた騒動は、前項で紹介した通り。背景や状況こそ違えど、米をめぐる混乱が社会全体に大きな影響を及ぼすという構図は、今も昔も変わっていないのです。
【書誌情報】
『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』
著:トキオ・ナレッジ
スーパーなどでの米不足、転売、価格高騰などで、ニュースやワイドショーでここ最近毎日のように取り上げられる今いちばんのホットトピック「米」。
備蓄米の放出により、古米がスーパーやコンビニで置かれるようになりましたが、味や品質、衛生面、値段、美味しく食べる方法など、普段何気なく食べていた米について興味をもって調べる人が増えてきました。
また、近年糖質制限という逆風もある一方で、健康志向や和食ブームの高まりにより「米」の再評価も進んでいます。
本書は、私たちの食卓に欠かせない「お米」にまつわる知識・文化・歴史・雑学などを、図解を交えてわかりやすく、楽しく紹介する教養本です。
「“令和の米騒動”はひとつの原因では語れない」
「年々減少する米の消費量 それでも起こる米不足」
「備蓄米ってなに? 米に消費期限はないの?」
「外国米が日本市場になかなか入れない理由」
「炊飯器に放置された保温状態の米の消費期限は?」
「白米より栄養価アップ!今人気の分づき米とは」などなど
読めば誰かに話したくなる米知識が詰まった一冊です。
この記事のCategory
オススメ記事

原因わからぬ「令和の米騒動」 スーパーから米が消えた様々な要因とは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

新米と古米の境界線は? 米の“年齢”と表示ルールとは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

日本の米は美味しいけど量は少ない?世界の米生産ランキングTOP10!【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】
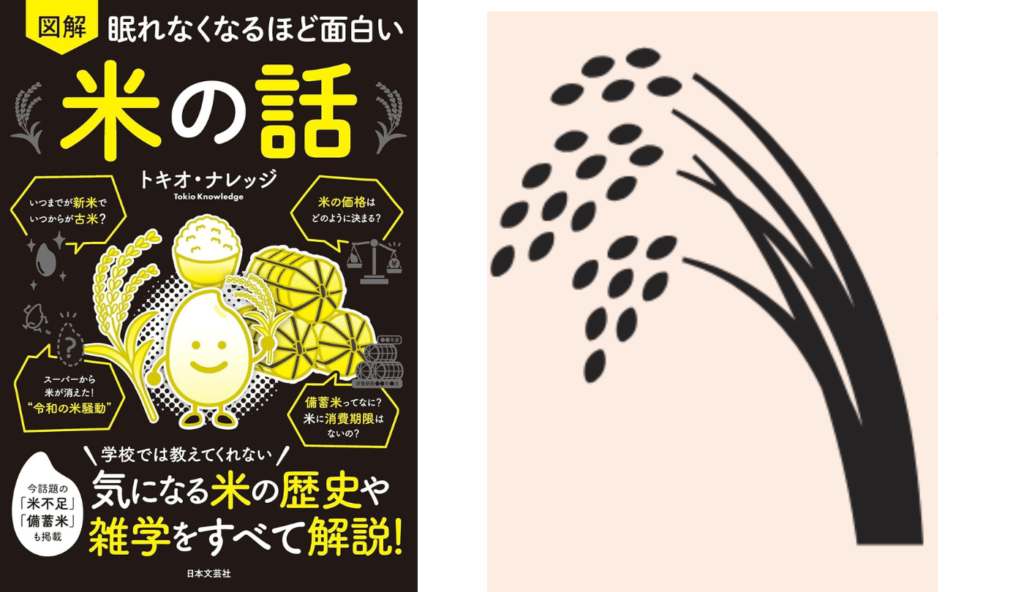
スーパーでの米の価格は誰がどう決める? 米価の仕組みを解説【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

武士の給料は米だった!? 江戸を動かした「石高制」のしくみとは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】

昔の人のアイデア満載! 発酵・乾燥・粉砕などなど…米でつくる食べ物と飲み物の知恵とは【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】
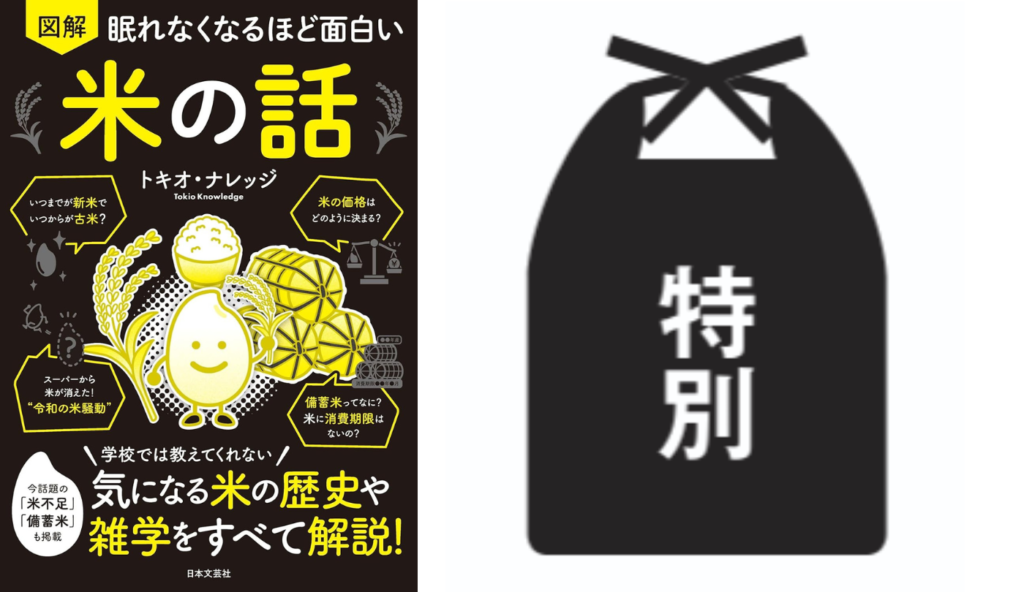
米の作り方で価格が変わる! 慣行・特別・有機栽培米の違いとは!?【眠れなくなるほど面白い 図解 米の話】