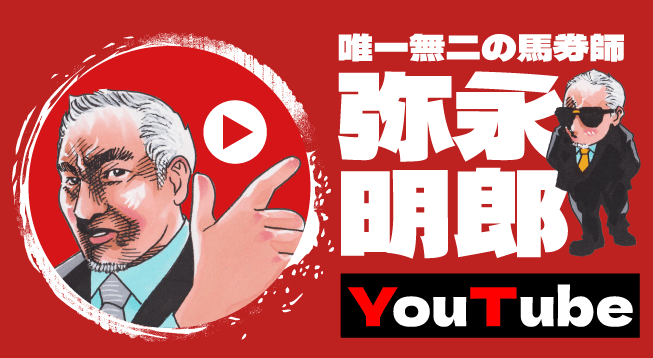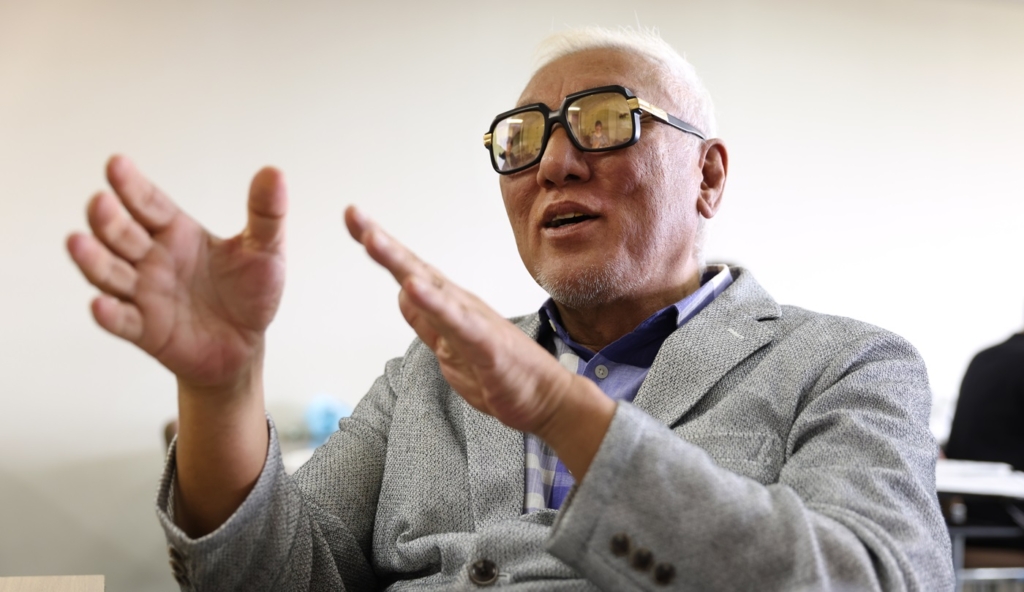『伝授』第16回 各競馬場の違いを伝授


洋芝の函館・札幌開催が終わり、10月18日からは野芝100%の新潟開催も始まる。今回は洋芝・野芝の差について俺なりの考えを書いてみたい。
また、各競馬場の違いについてもお伝えしよう。
・馬券を買う時に洋芝と野芝の違いはそこまで気にしなくていい
まず、洋芝と野芝の違いは根の張り方が異なる。野芝の方が、根っこが奥まで行くからしっかりしている。洋芝は逆に根っこが横に広がるけど、深くは張らない。野芝は北海道の寒さには弱いというので、北海道の競馬場では洋芝を使っている。
今年は北海道滞在中に馬場造園課の人とも結構話して、どういう状況かというのを聞いてみた。コースの内側で来年以降使う芝を3年分育てているのだけど、実際に見せてもらって歩かせてもらったりもした。
だけど、洋芝は時計がシンプルに速くないというだけで、俺はそんなに差はないと思っている。
函館の鬼と言われたエリモハリアー(2005~07年に函館記念を3連覇)にとって、函館競馬場のコースや芝が一番のど真ん中の適性だったことは間違いない。でも、エリモハリアーは函館で他の競馬場と同じ走りをしていただけで、それができない他の馬が負けただけとも言える。
だから洋芝が上手いとかいうのは一概にゼロとは言わないまでも、大した問題ではなく、その馬にとって走りやすいコースと時季的な問題だと思う。

・よく同じ扱いをされる函館競馬場と札幌競馬場だが、コース形態は大きく違う
函館競馬場と札幌競馬場は、コース形態が全然違う。函館競馬場は福島競馬場と似ていて、小回りで器用さが問われる。だけど札幌競馬場はコーナーの半径が大きく、意外と広くて乗りやすい。
函館の場合は開幕週だと内ラチ沿い走っている馬が圧倒的に馬券に絡む。ところが途中からCコースに変わると、コーナーで4頭分外を回った馬も勝つようになる。1頭の横幅が約1mとすると約4mくらい外を通っているわけだが、その距離ロスがあっても勝つのはなぜかというと、受けるプレッシャーの違いだと思う。多くの馬は外に馬がいると思い切って全身を使って走ることができない。それだったら距離損をしてでも伸び伸び走れる方が良いし、ジョッキーに関してもプレッシャーも感じないで済む。だから常々言っているけど、俺は本当に勝負するときの馬券は外枠だけ。

・新潟競馬場は唯一の野芝100%
新潟競馬場はJRAの競馬場で唯一100%野芝を使っている。東京競馬場や京都競馬場などは野芝とイタリアンライグラスという草を混ぜて芝コースを作っている。
とはいえ、芝による適性の差は大きく変わらないと思っている。ジョッキーは「新潟は走りやすい」とか「グリップが利く」とかコメントするけれど、正直なところわからない。
開幕週のパンパンの状態だったら、多少の差があるかもしれないけど、使ってからは一緒だしほとんど関係ない。
余談だが新潟競馬場を除いて、コースの外側はあまり使われることはない。競馬で使われない外の部分は手入れをしないので、コースの幅を10としたら、6くらいは手入れが行われていない。

・完全に平坦な競馬場はない
実はJRAの競馬場で、高低差が全くない平坦なコースは一つもなく、すべての競馬場で高低差がある。その中で一番高低差がないのは札幌で芝が70cm、ダートが90㎝。函館は芝・ダートともに3.5mある。だけど歩いても気が付かないレベル。ちなみに中山競馬場の芝コースが高低差5.3mだ。

中山の急坂のように明らかに目に見えてわかる坂がないと平坦という人がいるけれど、決して平坦ではない。
ただし札幌競馬場や新潟競馬場の内回りのようなわずかな高低差は、人間だって歩いても気が付かないのだから馬への影響はゼロだと思う。
一方、中山の急坂は上がるところで一度馬がストップする。強い馬はそこからまたエンジンをふかせられるけど、弱い馬は余力が残っていないからパッタリと止まってしまう。そこで逆転が起こるケースが多々あるから見ている方としてはスリリングで面白いよな。
次回は新聞のシルシの付け方について書いてみるから、楽しみにしていてくれ。