眠れなくなるほど面白い 図解 日本史
歴史は「流れ」がわかると面白いほどよくわかる! 日本列島の誕生から文明の発達、集落から国づくりへ、貴族社会から武家の台頭と下剋上、鎌倉幕府と室町幕府、織豊時代と江戸幕府、幕末の動乱から明治維新を経て近代国家への道、帝国主義と世界大戦の時代、新しい世界秩序へーー日本の通史を「まるごと図解」解説! 異説や日本史の謎に迫るコラムも充実。

藤原道長が紫式部や小野道風など多くの人材を見出し育て上げられた理由とは?【日本史】
長徳二年(九九六)七月、右大臣藤原道長は正二位左大臣に昇進。臣下最高位に就いたことで、摂関家、藤原一族の勢力争いは終わり、道長の一人天下となります。 そこで道長は娘彰子(しょうし)を入内(じゅだい)させ、一条天皇の中 […]

平将門と藤原純友が武士のルーツとなった理由とは?【日本史】
受領として地方に下った下級官人たちは、畿内はもちろん、日本各地に拡散して土着し、それぞれ武装勢力に成長します。律令政府の命令に従わず、独自の地方権力として振舞うようになります。 その最たる者が「承平(じょうへい)・天 […]
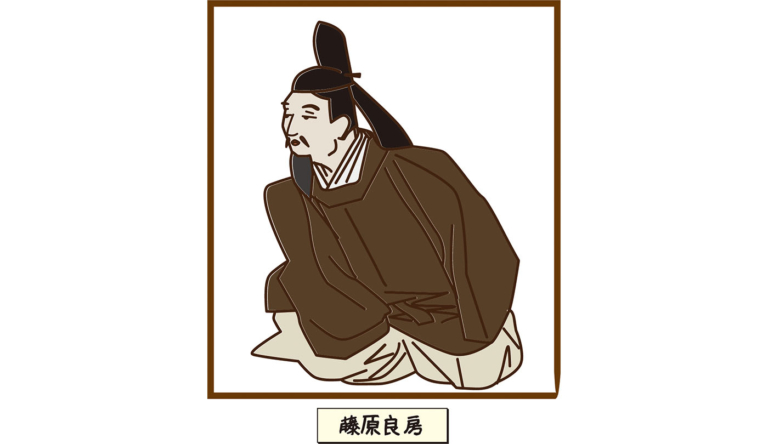
藤原一族が天皇の外戚となり、摂関政治を始めるまで勢力を拡大した理由とは?【日本史】
律令制度は唐の律令と同じではありません。難しすぎて現実には適用されず、現場の判断と裁量に任されました。 すると受領(ずりょう)として地方に下った下級貴族や土着の土豪、有力農民らが私的な利益追求を図るようになります。な […]

天台/真言両宗を宣伝する有力な手段となった最澄と空海が熱心に集めたモノとは?【日本史】
延暦(えんりゃく)二十三年(八〇四)、桓武(かんむ)天皇は遣唐使一行に最澄と空海を加えました。唐風化を急ぐ天皇と貴族たちにとって、これが予想以上の成果を挙げることになります。 最澄はわずか八カ月しか唐に滞在しなかった […]

平安京へ遷都し、坂上田村麻呂と共に桓武天皇がなし得た功績とは?【日本史】
桓武天皇は遅咲きの花でした。長い間、父光仁天皇の皇太子として施政に深く関与し、天応元年(七八一)四月、齢四十五歳にして第五十代天皇として即位しました。 施政方針も地味で、「簡易(かんい)の化(げ)」(安上りの政府)実 […]

聖武天皇が大仏建立を懇願した切実な理由とは!?【日本史】
聖武(しょうむ)天皇代、天平十五年(七四三)のこと。天皇悲願の詔(みことのり)を発します。前代未聞の大プロジェクトである大仏造立を国家事業として取り組むことを呼び掛ける宣言です。 しかし、誰も聞き入れませんでした。聖 […]

元明天皇が藤原京を離れ、平城遷都をした本当の理由とは?【日本史】
和銅元年(七○八) 正月のこと。 武蔵国から献上された和銅を記念して年号を改めた元明天皇は、住み慣れた藤原京を離れ、大和盆地北端に移転する決定を下します。いわゆる平城遷都です。 理由は色々挙げられますが、本当の理由は一つ […]

天武天皇が伊勢神宮を東国経営の拠点とし『古事記』『日本書紀』を纏めた理由とは?【日本史】
天武天皇は巨星天智天皇が病に倒れた時、自ら野に下り、挙兵して勝利した実力者であり、思う存分に辣腕(らつわん)を振るいました。 その際、国威発揚のため、新しい国づくりに着手する一方、大唐国には恭順の姿勢を示す必要上、似 […]

壬申の乱に勝利した大海人皇子が天武天皇となり始めた天皇親政時代とは?【日本史】
大化改新以来、三十年近く帝位に在った天智天皇(中大兄皇子)が病に倒れた時、大海人皇子(おおあまのおうじ)は「皇位は倭姫(やまとひめ)皇后に譲り、政治は大友皇子に任せればよい。私は出家する」と言い、吉野の山に向かいました。 […]

天皇の目前で中大兄皇子と中臣鎌足が蘇我入鹿を殺害!大化改新の真偽とは!?【日本史】
第三十五代皇極天皇四年、天皇家と度々衝突を繰り返す蘇我蝦夷(そがのえみし)・入鹿(いるか) 父子に対し、天皇中心の律令国家建設を目指す中大兄皇子(なかのおおえのおうじ)と中臣鎌足(なかとみのかまたり)が反発。宮中、天皇の […]

在位三十六年の推古天皇から五人七代の女帝が出現した理由とは?【日本史】
欽明天皇の死後、敏達(びだつ)、用明(ようめい)、崇峻(すしゅん)各天皇が皇位を継承しますが、崇峻天皇が蘇我馬子に暗殺されると順当な皇位継承者があったにも関わらず、敏達天皇の皇后炊屋姫(かしきやひめ)が第三十三代推古(す […]

聖徳太子が天皇中心の国造りに起ち上がった理由とは?【日本史】
継体(けいたい)天皇の嫡男、第二十九代欽明(きんめい)天皇代のこと。百済(くだら)聖明王が釈迦仏一体、経論若干巻を献上し、仏像礼拝の功徳を称えました。 すると天皇は「これほど微妙な法を聞いたことがない」と歓喜して群臣 […]
