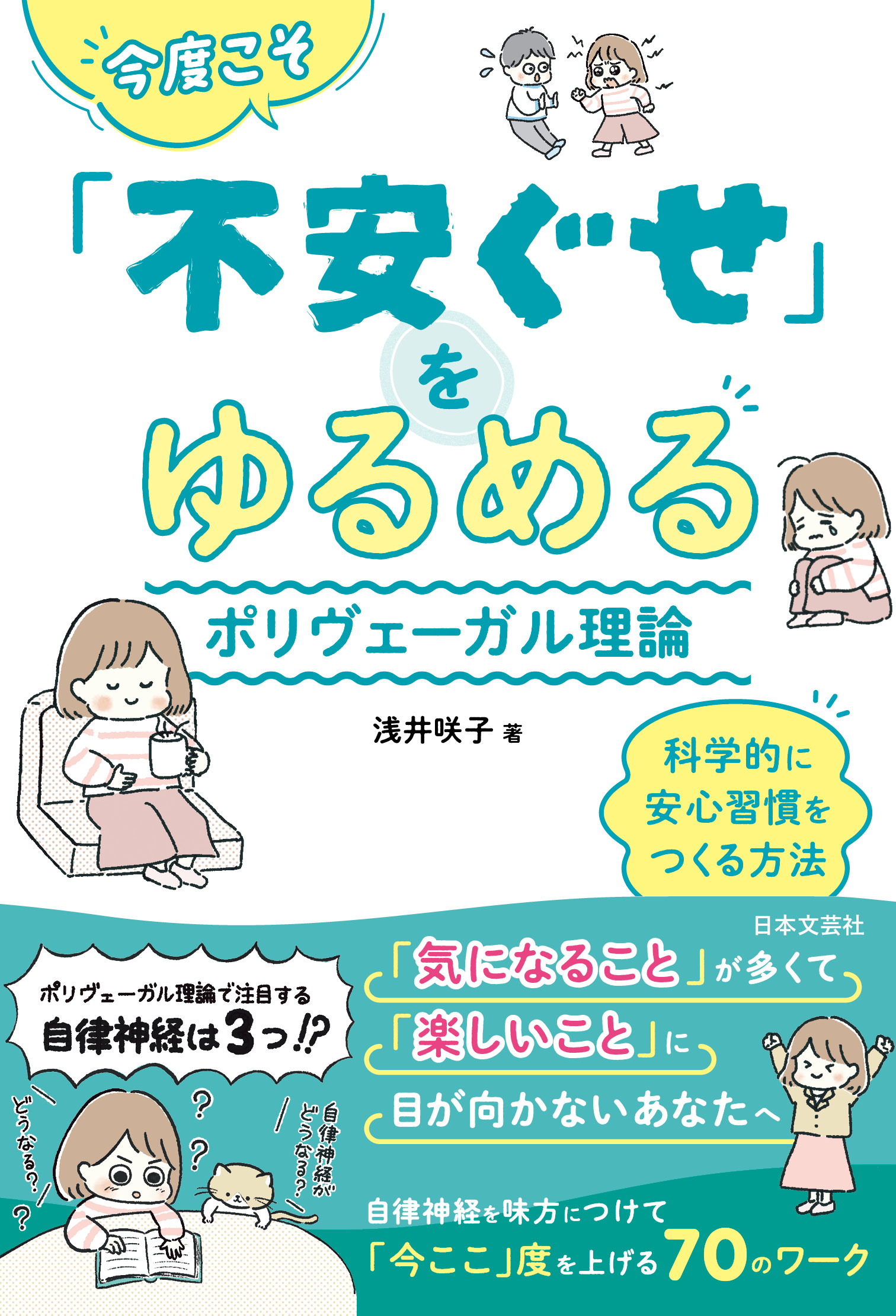不安や緊張、イライラに悩むすべての人に知ってほしい 自分を整える方法『今度こそ「不安ぐせ」をゆるめるポリヴェーガル理論』浅井咲子先生インタビュー【前編】
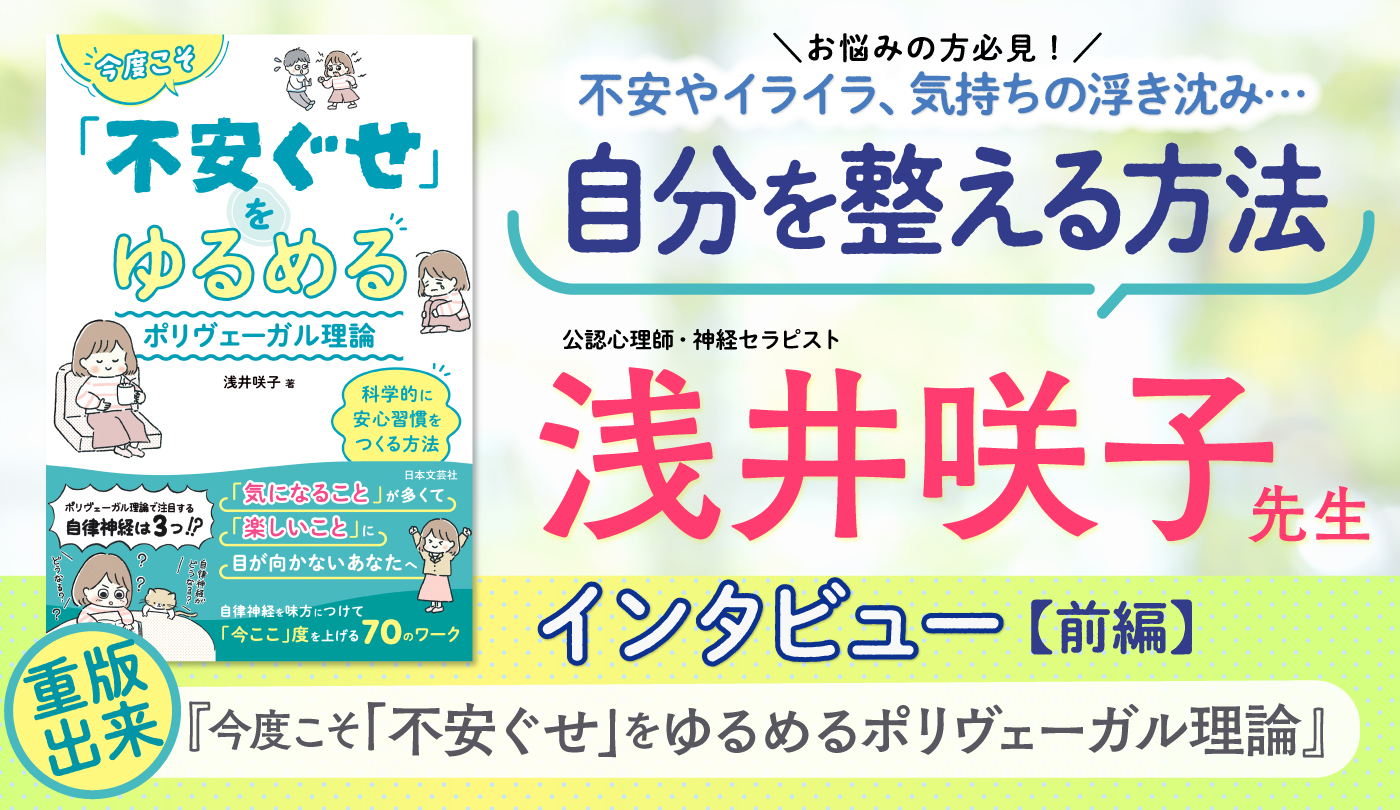
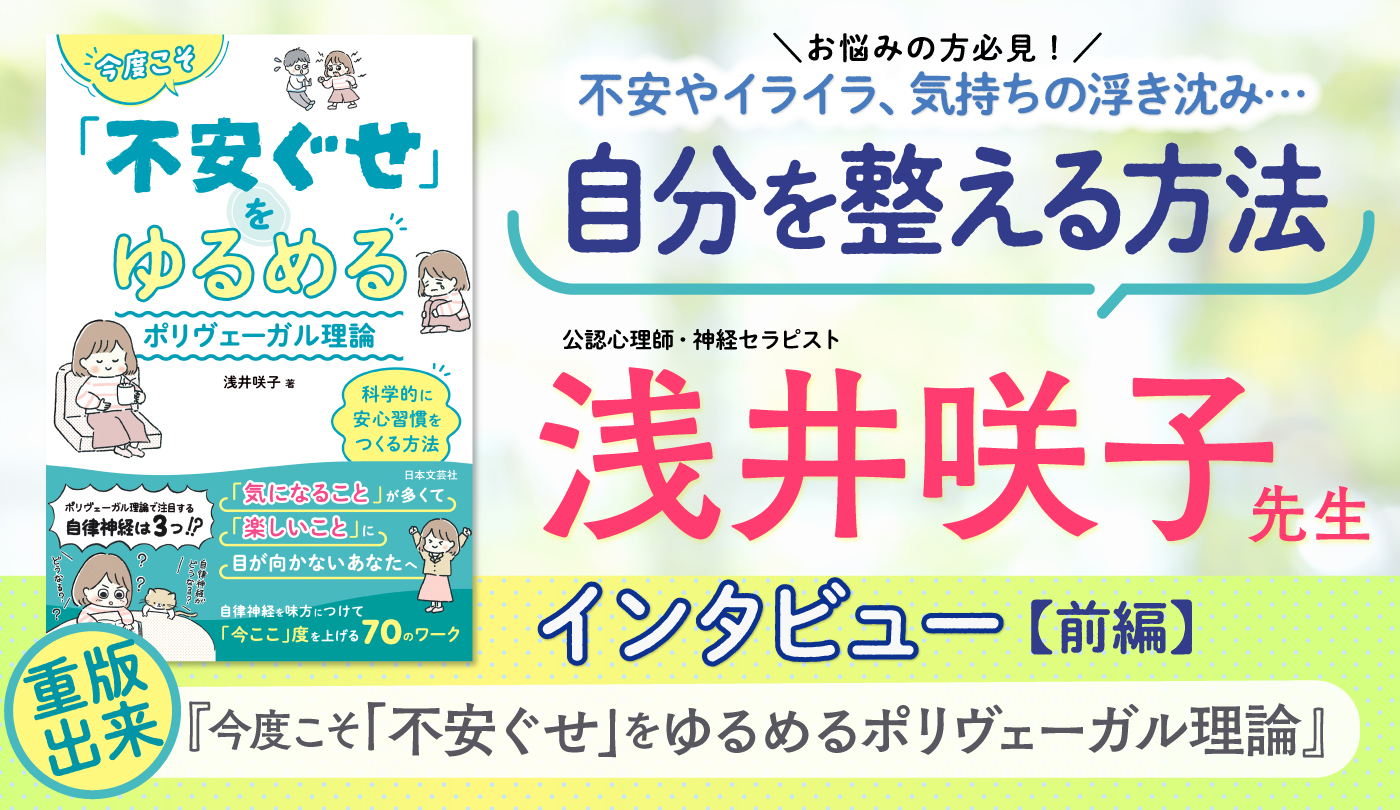
不安やイライラ、気持ちの落ち込みに悩む方必見! 『今度こそ「不安ぐせ」をゆるめるポリヴェーガル理論』(日本文芸社)は、ポリヴェーガル理論という科学的な視点で不安のしくみをひもとき、ゆるめる方法を提案してくれる1冊。ところで、ポリヴェーガル理論って何? そんな初歩的な疑問から心が不安定になるしくみまで、気になる疑問を著者で神経セラピストの浅井咲子先生に聞きました。
取材・文:高島直子
最近話題のポリヴェーガル理論って?
近年、心理療法やトラウマケアに限らず、ヨガなど身体ケアにも取り入れられることが多くなった「ポリヴェーガル理論」。浅井先生はその第一人者としてカウンセリングや講師としての活動も行っています。
——最近注目されている「ポリヴェーガル理論」は、新しい考え方なのですか?
浅井 そうですね。1994年にアメリカの神経科学者スティーブン・W・ポージェス博士によって提唱された理論で、神経科学の中でもまだまだマイナーな理論です。
だから、「ポリヴェーガル理論をベースに、不安を解消するためのワークをたくさん紹介する本をつくりませんか?」とお声掛けいただいたときには、相当マニアックなところに目をつけてくださったなと思いました(笑)。
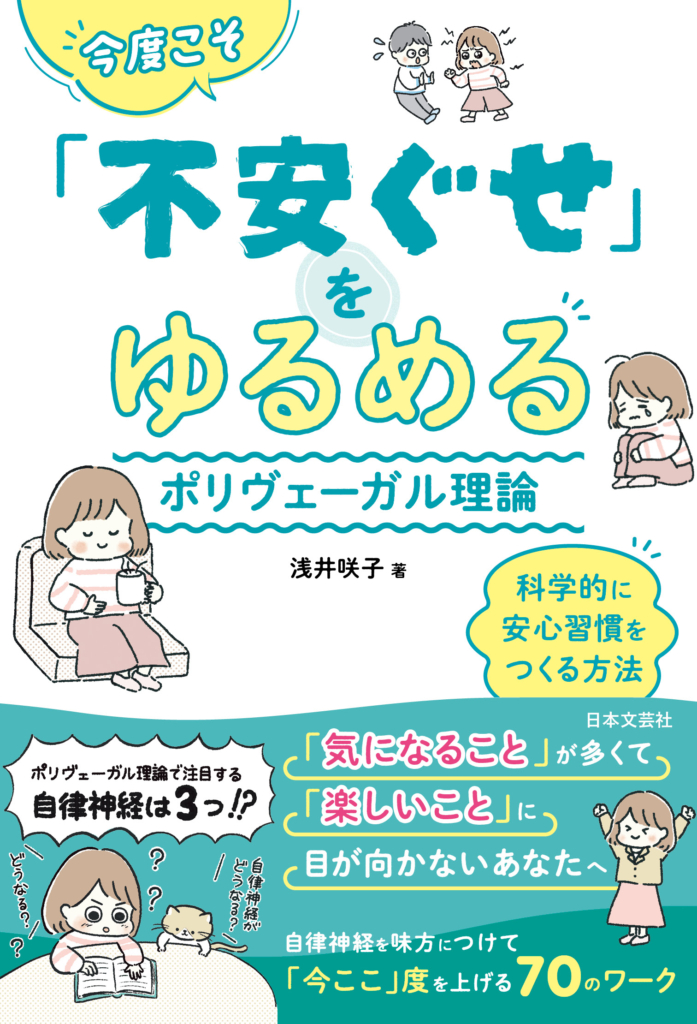
——「ポリヴェーガル理論」とはどんな理論なのでしょうか。
浅井 大きな特徴は、自律神経の働きを「交感神経」と「副交感神経」の2つではなく3つに分けて考えているところです。人の体には自律神経が張りめぐらされていて、この自律神経が心身のバランスを調整してくれている……ということはよく知られていますよね。
自律神経は、活動時には「交感神経」が、休息時には「副交感神経」が優位に働くというのが従来の考え方なのです。
ポリヴェーガル理論では、副交感神経をさらに2つに分けて捉え、これに交感神経をプラスした全部で3つの神経に注目します。
①背側迷走神経系……ひとりでくつろいでいるときにはこの神経がほどよく働き、死の脅威を感じたときにはこの神経が強く働きシャットダウン(停止)して自分を守る。
②腹側迷走神経系……哺乳類特有の神経で、誰かとつながることで安心感を覚える。
③交感神経系……危険を感じたときにこの神経が強く働き、攻撃的になったり(戦う)、防御的になったり(逃げる)する。

——おもしろいですね。危険を感じると攻撃性や防御性が強くなり、さらに強い危機を感じるとシャットダウン(停止)するというのは、すごく動物的で納得できます。
浅井 そうなんです。しかも、自分が安全か、危険かを無意識のうちに察知する「ニューロセプション」というシステムがわたしたちには備わっているので、頭で考えるより先に反応が出るんです。それこそが「なぜか不安」の原因です。
理由もわからずイライラしたり緊張したり不安になったりするのは、体が頭で考えるより先に危険を察知し、交感神経または背側迷走神経が働いているからだと言えますね。

「不安ぐせ」は日本人の国民病!?
——本書では不安やイライラに振り回されてしまうくせを「不安ぐせ」と呼んでいますが、浅井先生も不安ぐせを感じることはありますか?
浅井 もちろん! 書籍の「はじめに」でも書きましたが、不安やイライラがない日はないくらいですよ。
私の場合は、幼少期の影響もあってなかなか不安が解けず、周囲に安心感をもてないまま日々を過ごしました。安心を手に入れたくて、状況を整えたり、環境整備をしたりしてもなぜか落ち着かない。そんな経験を何度もしてきました。
でもポリヴェーガル理論を知って、安心・安全というのは外側ではなく身体の内側の感覚から生まれるものなんだと理解できたんです。
——「不安ぐせ」を抱えやすい人の傾向ってあるのでしょうか?
浅井 カウンセリングに来てくださる方は、本当にまじめな方が多いです。まじめで、誠実で、がんばりやさん。そういう方は自分にプレッシャーをかけて物事をきちんとやり遂げようとしますよね。そんな勤勉さと引き換えに心と身体が緊張状態になってしまっている方にたくさん出会ってきました。
あと、海外の方を見ていると、日本人はとくに「不安ぐせ」を抱えやすい国民性だなと感じます。個人主義の海外と違い、集団で行動することが習慣的に行われているからでしょうか。自責の念が強く、努力をし、まわりに気を使って一生懸命仕事をしている。
日本人はまさに一億総インポスターシンドローム*。そりゃ不安にもなるよねって思ってしまいます。
*インポスターシンドローム(症候群)とは、成功を収めていても自信が持てず、自分を必要以上に過小評価してしまう心理状態のこと。
——カウンセリングにいらっしゃる方も増えている印象ですか?
浅井 コロナ禍以降はとくに増えたように感じます。
コロナ禍は人とのつながりがどうしても希薄になりやすい時期でしたから、腹側迷走神経を使う機会が減ってしまいました。人とのつながりによって安心感を得ることができる腹側迷走神経が十分に刺激されなかったことで、サバイバルの状態(逃げたり攻撃したりする交感神経が優勢)になりやすくなってしまったのでしょう。
つらいのはあなたのせいじゃなく、自律神経のせい
——「不安ぐせ」にもさまざまな要因があるのですね。
浅井 そうですね。でも、知っておいてほしいのは、不安はこれから起こるかもしれない危険に対して生じる感覚で、自分を守るための自然な反応。
「なんでわたしっていつもこうなの?」と自分の性格や考え方を責めてしまいがちですが、それは自律神経の働きによるものなのです。ほんの少し、神経系の仕組みを知るだけで自分自身を整えやすくなります。
私自身、ポリヴェーガル理論に出会ったことでそうした実感がもてました。だから、多くの人に「神経を味方につける」感覚をもってもらえたらと思い、本書を書いたんですよ。
インタビュー後編では、ポリヴェーガル理論を用いた「不安ぐせ」をゆるめるワークをご紹介します!
【著者紹介】
浅井咲子(あさい・さきこ)
公認心理師、神経セラピスト。立教大学卒業後、外務省在外公館派遣員として在英国日本国大使館勤務。その後、米国ジョン・F・ケネディ大学院にて、カウンセリング心理学の修士課程(身体心理学専攻)を修了。オークランドの地域カウンセリングセンターにて研修を行う。
帰国後、教育センターや企業内で相談員として勤務。2008年、セラピールーム「アート・オブ・セラピー」を設立し、自己調整とレジリエンスのある生活を提案し続けている。著書に『不安・イライラがスッと消え去る「安心のタネ」の育て方』(大和出版)、『「今ここ」神経系エクササイズ』『「いごこち」神経系アプローチ』(梨の木舎)、翻訳書に『子どものトラウマ・セラピー』(雲母書房)、『レジリエンスを育む』『発達性トラウマ治癒のための実践ガイド』(岩崎学術出版社)、『トラウマによる解離からの回復』(国書刊行会)など。
ブログ https://ameblo.jp/artoftherapy/
HP「ART of therapy」 https://assakijp.wixsite.com/artoftherapy
【本記事の取材・文】
高島直子(たかしま・なおこ)
フリーランスライター・編集者。生きもの、こども、料理などのジャンルを中心に、幅広く書籍や雑誌の制作に携わる。
【書誌情報】
『今度こそ「不安ぐせ」をゆるめる ポリヴェーガル理論』
著:浅井咲子
3つの自律神経を味方につけて
〈不安ぐせ〉を〈安心ぐせ〉に変える!
「次から次へと心配ごとがでてくる」
「ニュースやSNSで不安になりがち」
「イライラする」
「ストレスに弱い」
「気持ちの浮き沈みがはげしい」
「やる気が起きない」
などの〈不安ぐせ〉を抱える人へ。
ポリヴェーガル理論は、ステファン・ポージェス博士によって提唱された自律神経系の神経理論です。
自律神経を、1つの交感神経と2つの副交感神経(背側迷走神経と腹側迷走神経)の3つで捉えます。
本書では「セオリー」「テクニック」「ワーク」に分けてわかりやすく紹介します。
セオリー
→難解なポリヴェーガルを、イラスト図解を使いながらわかりやすく解説。用語もなるべくかんたんに紹介します。
テクニック
→「眼輪筋を動かす」「相槌は高めの音程で」など、ポリヴェーガル理論を活かした会話術、仕事術、休み術などを紹介します。
ワーク
→「脳幹タッチ」「太陽をのみこむ」「人と歩調を合わせる」など、日常のなかのちょっとした工夫でほっと気持ちを落ち着けるコツを紹介します。
本当は必要ではないのに過剰に防衛したり、考えても仕方がないことにイラっとしたり、不安になったり。
そうしたもったいない時間を減らして、「今ここ」にある幸せを感じ、安心できるようになるためのメソッドです。
【イラスト/まんが制作】
高木ことみ(たかぎ・ことみ)
ゆるくてかわいいイラストを制作するイラストレーター。とくに、難しい内容を図やイラストを用いてわかりやすく伝えることが得意。見ている人に親しみを感じてもらえるような表現を心がけている。おもな作品に『ゆるゆる稼げるWebライティングのお仕事はじめかたBOOK』(技術評論社/表紙・本文イラストを制作)など。
note https://note.com/t_kotomi
X https://x.com/T__kotomi
この記事のCategory
求人情報
オシャレバルでのホール・調理補助スタッフ/20~30代活躍中 未経験から月給30万円をGET
株式会社M-SUN
勤務地:大阪府雇用形態:正社員給与:月給30万円~スポンサー:求人ボックス
製造スタッフ/年間休日120日!研修制度充実で未経験でも安心
株式会社エイジェック名古屋
勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給21万円~スポンサー:求人ボックス
児童指導員/多機能型施設/日曜休み/「できた!楽しい!」を実現する感覚統合とABA療育に特化した施設/月給23万円~/充実研修でさらに成長も
このき豊田校
勤務地:愛知県雇用形態:正社員給与:月給23万円~35万円スポンサー:求人ボックス
設備管理
株式会社ビルテック
勤務地:東京都雇用形態:契約社員給与:日給1万2,000円スポンサー:求人ボックス
准看護師/かけもちバイトにもおすすめ/精神科や訪問看護の経験は不問/週1日から勤務OK!/採用強化中
訪問看護ステーション 晴れやかな空
勤務地:愛知県雇用形態:アルバイト・パート給与:時給1,620円~1,710円スポンサー:求人ボックス
商業施設の駐車場警備スタッフ
シンテイ警備株式会社
勤務地:東京都雇用形態:アルバイト・パート給与:日給1万500円~スポンサー:求人ボックス